川田順造『〈運ぶヒト〉の人類学』要約
「運ぶ」という行為は,ヒトが世界に拡散していくことを可能にした。ヒトの「運ぶ」技術は,その地域ごとのヒトの身体的特徴と地形や気候などの生態学条件よって異なる指向性を持つ「文化」として,人々に担われている。
人類の発展は「運ぶ」能力のおかげか?
「運ぶ」という観点から文化を紐解く
なぜヒトが世界に拡散し,高度な文明を築くことができたのか。それは,ヒトが直立二足歩行によって言語,大きな脳,そして「運ぶ」という能力を得たためである,というのが本書の出発点だ。
「運ぶ」というのはそんなに重要なのか,と思わされる。しかし,著者によれば「運ぶ」という行為,特に「道具を使って運ぶ」という行為には「文化」が関わっているという。
本書の書かれた目的は以下のとおりである。
「運ぶヒト」を問題にする上で,ヒトを他の生物とも共通の「知覚=運動有機体」一つと見て,そのなかでヒトの文化の特徴を明らかにしよう(p.54)
できる・できないは育った文化に左右される
テレビで,発展途上国の人々が頭の上に大きなものを載せ,器用に歩いている姿を見ると「すごい」と思わされる。また,(私には)オンボロ(に見える)台車に,少しでもグラつけば落ちてしまうのではないかと思えるほどの荷物を載せ,混み合う街中を何気なくぬっていく人を見ると,これまた「すごい」と思ってしまう。
現代日本人である私は同じようなことは絶対にできないと考えると,やはりそこには育った文化に差があるのではないかと思わされる。そして,文化がいかに個々人の技能の幅に影響を与えているか,とも思わされる。
本書によると,「運ぶ」という行為を含めたヒトのあらゆる営みは,最広義での「文化」と言える。文化は最終的には「個人」によって担われるが,その「個人」の集合体である「社会」から影響され拘束されてもいる。
つまり,私が頭上にものを載せてスタスタと歩くことができないのは,文化のせいだと言えるということだ。さらに言うと,運ぶためにどのような「道具」を作り,使うかというのも「文化のせい」にできるという。
ヨーロッパで蒸気機関が発明された理由を「道具」で説明
「道具」と「文化」について考えるきっかけとして,蒸気機関の発明について見てみよう。
なぜ,産業革命がヨーロッパから始まったのか。道具と人間の関係に着目すると,その糸口が見えてくる。
人間を動かせないために努力を惜しまないのがヨーロッパ人
産業革命の鍵となるのは,蒸気機関という動力の発明である。蒸気機関がイギリス,つまりヨーロッパで生まれたのには,ヨーロッパの人々の道具に対する指向性が関係しているという。
人間がどのような道具を作る・使うかという指向性は,以下の3つに分類することができる。
- ①道具の脱人間化(「二重の意味での人間非依存」)
- (1)人間の巧みさに依存せず,誰がやっても同じような結果が得られるように道具を工夫する,(2)人力以外のエネルギーをできるだけ利用する …ヨーロッパ
- ②道具の人間化(「二重の意味での人間依存」)
- (1)人間の巧みさによって単純で機能未分化な道具を多機能に使いこなす,(2)人力を惜しみなく投入 …日本
- ③人間の道具化
- 圧倒的な自然の猛威のなかで,自然と人間を共に支配する至高の力への,依存の中の働きかけ …アフリカ
ヨーロッパの人々は「道具の脱人間化」という指向性を持ち,その「人間以外のエネルギーを有効に使おうとする執念」(p.136)が蒸気機関を発明させたのである。
道具を工夫するのは「はたらく」のを「罰」を考えるから
では,なぜヨーロッパでは「道具の脱人間化」という指向性が生まれたのだろうか。著者は人々の「労働」に対する考え方に着目する。
キリスト教世界では,「はたらく」というのは人間の原罪を贖う行為である。禁断の樹の実を食べた人間に,創造神ヤハウェが課した罰が「労苦」であった。
そのためヨーロッパでは,日本やアフリカに見られるような労働に対する感謝やねぎらいという考え方や,それを表す言葉がない。
例えば,日本語の「ご苦労さま」にあたる,労をねぎらう言葉はフランス語にはない。逆に,アフリカのモシ語には「ご精が出ますね!」「あなたの骨の折れる労働ともに!(頑張ってくださいの意)」など,働いている人を励ます慣用句が多くある。
キリスト教思想の根付いたヨーロッパでは,日本やアフリカとは違い,「はたらく」ことを「労苦」「罰」だとする考えがある。その考えが,労働するときにはなるべく人間以外のものに頼り,人力を省こうとする「道具の脱人間化」という指向性を生み出した。
運ぶ身体・文化・道具
本書の主張をまとめてみよう。
なぜ,地域によって運搬の道具や方法が違うのか。それは,それらの道具や方法がその地域の人々の文化に影響されているからだ。
では,そのような文化の違いはなぜ生じるのか。それは,その地域の人々の身体的特徴や生態学的条件(地形や気候など)に応じて,最も効率的な運搬方法が決定されるからである。
感想: 運搬が人類の発展に寄与したというのは大げさ
★★★☆☆
写真や図が数多く載せられており,眺めているだけでも楽しい本だった。写真の多さはこの本の魅力の一つでもあるので,興味をもった方はぜひ本を手にとって見てほしい。
ただ,たぶんこの著者,アフリカや日本の文化が好きでヨーロッパの文化は「嫌い」なんだろうな,と思わせる記述が散見される。とにかくラクをしようとするヨーロッパの考え方を「横着な! けしからん!」とでも言っているように感じられ,読んでいて「は?」と思わされた。
さらに言うと,客室乗務員のことを「スチュアーデス」呼ばわりし,その上で日本人「スチュアーデス」の歩き方にケチをつけているように書いてあり,ただのセクハラオヤジかよ,とも。20年前とかの本じゃないですよこれ,2014年出版なんです。
せっかくなのでかなり個人的な感想も書かせていただいたが,これらの文句は特に内容に関わるものではない。内容に関わることを1つだけ言おう。
「運搬」ではなく「適応」「創造性」
「運搬」が「言語」と同じくらい人類の拡散・発展に寄与している,というのが著者の立場だ。では,「運搬」は生物の中でヒトに特別なものなのだろうか。
「運ぶ」動物といえばアリを思い浮かべる。アリは,自分の体重の何倍もの獲物を運んで巣に持ち帰ることができる。「運ぶ」ということだけみると,ヒトよりもアリのほうが優れているように思える。
「運ぶ」ことにおいてはより優れているアリよりも,ヒトの方が文明を発展させたと考えると,「運ぶ」以外のところに人類発展の秘密があるようだ。
ヒトがすごいのは,ものを運んで移り住んだ新たな土地に適応することができたところなのではないか。また,同じヒトでも地域や個人によって身体的特徴は違う。ヒトは,自分の身体に合わせて運ぶ方法や道具を工夫した。そういう創造性が,他の生物と一線を画すものなのではないか。
「運搬」が「言語」や「発達した脳」と同じくらい人類の発展に寄与した,というのは言い過ぎである。
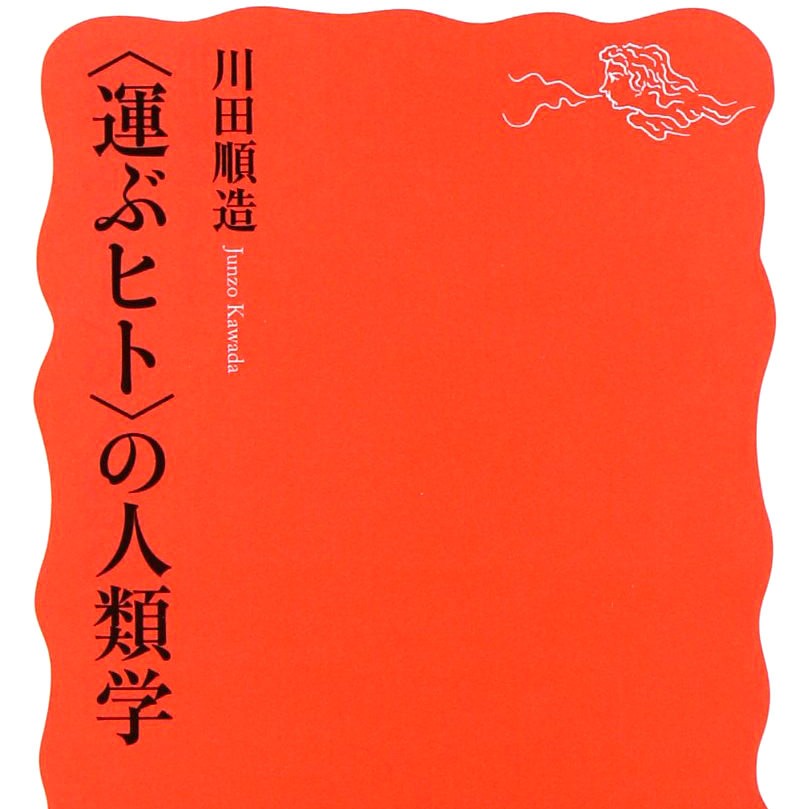


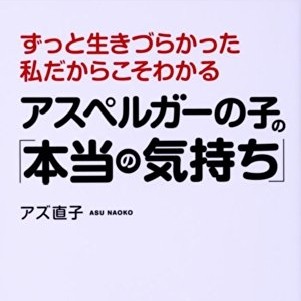

コメント