市川伸一『勉強法が変わる本』要約
勉強の成果は,どのような方法をとるかで大きく変わる。心理学的な立場からすると,「丸暗記より理解へ」「結果より過程へ」「量より内容へ」という方向で,勉強法を改善することができる。
勉強法を根本的に見直すならこの本―「ひたすら練習あるのみ」をぶった切る
(1)漢字,(2)計算,(3)英単語。この3つは「やるっきゃない」と誤解されている御三家だという。「ひたすら練習あるのみ」が間違いだとすれば,これら3つの効果的な学習方法はどのようなものだろうか。
- (1) 漢字
- ①いつも同じ筆順で,手の運動感覚として覚える。②漢字の構成要素になじみ,それぞれの漢字の構造を理解する。
- (2) 計算
- 工夫して簡単な形(小さい数字,単純な式など)にしてから計算する。「出てきたらそのとおりに実行」してはいけない。
- (3) 英単語
- ①日本語と英語を対にして,頭にたたきこむ。②語と語の関係や文例など,英単語どうしの関係を重視してイモヅル式に覚える。何度も手で書くのは意味を思い出すには効果がない。
記憶理論から見た記憶法・暗記法
分散学習<集中学習
記憶するために反復練習するなら,いちどきに時間をつめて行う「集中学習」より,休憩時間をはさんだ「分散学習」のほうが,学習の伸びも速いし,忘れにくい。
休憩時間も含めれば分散学習はトータルで長い時間になってしまう。しかし,試験前にあわててつめ込むよりも,普段から少しずつ勉強しておいたほうが,はるかに有効である。
体系づけ
記憶に対する認知主義の考え方によると,既得知識を使いながら情報を関連付けることによって,頭の中に新たな知識構造が作られていくそうだ。つまり,体系づけると覚えやすくなるということだ。
では,知識を体系づけるにはどうしたらいいか。それには,インデントや矢印などを使ってノートを作ることだという。本書では,歴史と数学のノートのまとめ方が紹介されていたが,学校の先生の板書をノートに写したり,そのノートを見返したりするのも効果的ということになろう。
好きな教科ならすぐに覚えられるというのは,自分に興味があって知識が体系づけられ,「努力して暗記している」という感じを持たないからだそうだ。
嫌いな科目ほど,こうした関連づけを怠って,「覚えることばかり多くてつまらない」と思っていることはないだろうか。(p.52)
これは耳の痛い一言だと思うのは,私だけではないだろう。
数学の勉強法: 問題を解いていくだけでは学力がつかない
数学の苦手な諸君,あなたの数学勉強法は次のようになってはいないだろうか。
①参考書や問題集の問題を解く。
②解ければ答え合わせをする。解けなければ正解を見る。
③合っていればマルをつけ,間違った箇所はノートに赤字で書き込む。
④何日か期間をおいて,同じ問題を再びやってみる。(p.127)
本書によれば,このような「勉強はテストで点をとるためにあるのだから,テストのときと同じことをくり返して慣れればよい」という学習観では学力は身につかないそうだ。
本書では,次のような数学の勉強法が提案されている。
- 問題を解く前に,教科書や参考書の解説部分をよく読む
- 公式は,「どうやって導いたか」というポイントを押さえる
- 教科書の例題クラスの問題は,ただちに解ける状態にしておく
- 間違えたら,なぜうまく解けなかったか,を考える
- 「こうだといいのに」と考え,知っている問題にもちこむ
感想:
★★★★☆
勉強法に関する本はごまんとある。この本の特徴は,心理学的な立場から勉強法や学習観を見直すというところだ。その点,著者の成功体験にものを言わせただけの勉強法とは違う。
もう一度言おう。この本の目的は,心理学的な立場から勉強法を見直すことだ。つまり,「こうすればオッケー」という勉強法を紹介してくれるわけではない。
この本に書いてある効果的な勉強法の原則をヒントに,自分で自分にあった勉強法を見つけてもらう,というのがこの本の趣旨というわけだ。私はそこに強く惹かれる。
一人ひとり状況や得意不得意が違うのに,「こうすれば絶対に点数が上がる」なんていう勉強法が存在するはずなどない。そこを素直に認め,最終的には自分の学習方法を作るのは自分自身だ,と主張する著者の考え方に好感を覚える。
本書は,巷にある勉強法の本何十冊分の価値がある本だと思う。この本を読み終えた今は,しばらく勉強法に関する本は読まなくていい,という気分だ。
最後に,印象に残った箇所を2つ,共有したい。
「勉強」は小・中・高校生にとっての「仕事」
「なんで勉強しなきゃいけないのー?」と聞かれたらどう答えるか。これは,親や教師になったら突き出される課題だ。この問いに対して,本書は次のように答える。
テスト勉強をしていれば十分というわけではないが,テスト勉強だからといってバカにして,高校で習うような知識の習得や問題の解決すらしなかった(できなかった)人が,社会に出て急に優れた問題解決的な仕事をすることはめったにない。(p.145)
同意だ。「勉強は勉強でしかない」というのは,勉強を過小評価している。社会に出て何年も働いている人が学校の勉強を振り返ると,そう感じられるかもしれない。しかし,現在進行形でで勉強をしている子どもたちにとっては違う。
「子どもが学校で勉強をする」というのは,社会人に置き換えるならば「会社で仕事をする」ということになる。つまり,「目の前にあるやらなければならないこと」という意味では,仕事も勉強も同じということである。
だから,親や先生が子どもたちに勉強するように励ますとするなら,それは,将来その子どもが真摯に仕事に向き合うような態度を養うという意味で,とても立派なことだと思う。
勉強は「やらなければならない,つまらないこと」ではない
著者は,日本人の勉強観にも一石を投じている。
(「勉強」という言葉は)日本でも,押しつけ的,受け身的に学習するというニュアンスを込められることがある。しかしものは考えようで,ぼくは,「勉めて強くなる」つまり「自分を鍛えてパワーアップする」ということだと考えるようにしている。勉強によって,自分が広がっていく。そういう感覚をぜひつかんでほしいものである。(p.194)
私も,日本人の勉強観は好きではない。勉強はやらなければならないことだ。だが,〈やらなければならない=辛い〉ではない。
勉強でも仕事でも,自分のためになる,自分の人生を豊かにしてくれると考えるだけで,だいぶ違ったように感じられるのではないだろうか。少なくとも私は,そんな前向きな考えで勉強にも仕事にも打ち込みたい。
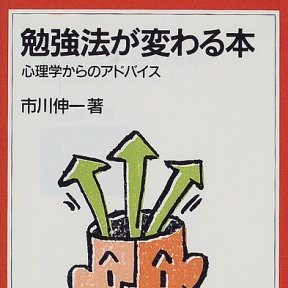




コメント