渡辺二郎『はじめて学ぶ哲学』要約
哲学は,世界全体が根本的に何であるのかを明らかにしようとする「世界観」であり,自己の人生の意義を考えて「良く生きよう」とする「人生観」である。科学的知識によって失われた主観的な真理の把握には,自分の経験を直視し,先哲の大きな遺産に学ぶ理論的・論理的探究が要求される。
哲学は常識,学問,宗教の欠陥を克服する
本書は全体で15章からなる。
- 第1部(1~6章):哲学の主題と方法
- 第2部(7~13章):哲学思想史
- 第3部(14~15章):あるべき現代哲学の方向
普段「科学」をやっている私の立場からしては,第1部,特に第3~4章が「おもしろい」と思えた。なので,そこを中心にご紹介しよう。もちろん,哲学の内容に踏み込んだ第2~3部も収穫が大きかったことは言うまでもないが。
常識・学問・哲学
第2章の2「求められる「知」について」では,知識を「常識的知識」「学問的知識」「哲学的な知」の3種類に分けていた。自然科学をはじめとする「科学」的知識はもちろん「学問的知識」に入る。
それぞれの「知識」に対する著者の説明をまとめると,以下のようになる。
| 種類 | 特徴 | 限界 |
|---|---|---|
| 常識的知識 | 知的探究を始める前提となる「先行的知」 | 一種の「偏見」/時と所に制約され「相対性」「特殊性」をもつ |
| 学問的知識 | 常識的知の「相対性」を乗り越え「客観性」「普遍性」をそなえた知 | (1)特定の事象以外を捨象するあまり細分化・専門家し「全体」がわからなくなる/(2)「客観的」たるために自己を捨てるため,価値・目的・目標・意義・意味の問いには答えない |
| 哲学的な知 | (1)世界が全体として何であるのかを明らかにしようとする/(2)人生の意義・価値・目的を考え抜き「良く生きよう」とする | なし |
本書によると,哲学とは様々な制約のある「常識」にも,部分に焦点を当て「主観」を見失ってしまった「学問」にも扱えない,「人生観・世界観」の「根本知」の探究である(p.44)。
芸術・宗教・道徳と哲学
「人生観・世界観」は哲学だけのものではない。芸術・宗教・道徳も共通の主題を扱っている。続く第3章の2では,芸術・宗教・道徳と哲学との違いについて書かれている。
端的にいうと,哲学と,芸術・宗教・道徳とは,「内容」の上では関連があるが,「形式」の上では大きな差異を持つ。共通する「内容」というのは,「人生観・世界観」のことだ。では,「形式」の上ではどのような差異があるのだろうか。それをまとめると以下のようになる。
- 芸術:具象的・直感的な表現をする「美」
- 宗教:啓示をひたすら信仰する「聖」
- 道徳:行為的な規範を命令する「善」
- 哲学:多様のなかに統一を保持する「真」
哲学は,芸術・宗教・道徳の射程を十分に取り入れた上で,さらに広く深く「人生・世界」「自己と存在」という問題を提示するものだという(p.60)。
感想
★★★☆☆
先述した表で,哲学的な知には限界は「なし」とあったことから推測できたと思うが,著者は「哲学最強!!!」派である。科学にも芸術にもなし得ないことが,哲学にはできちゃうんだぜ~ってな話だ。
それに対してもの申す。
「学問・科学<哲学」というのは誤りではないか?
常識を越えるために学問や哲学がある,というところまでは同意できる。だが,著者の学問・科学否定には賛同できない。
私からすれば,学問・科学と哲学は,真理の探究という点において共通する。しかし本書は,哲学が優れたものであることを言いたいがために,真理は哲学だけが見極められるものだと主張していた。そのため,学問・科学も真理を求めるということ,そしてその点において学問・科学と哲学には共通点があるということが見えなくなっていた。
これが見えなくなることで,さらにもう1つ,重要な点が見逃されてしまった。
「客観」は学問にも哲学にも必要なプロセス
見逃されていたもう1つのことは,学問でも哲学でも,真理の探究には客観的になるプロセスが必要だということである。
著者は「客観」という属性を「学問・科学」にカテゴライズし,「学問・科学」を徹底的に否定したた。そのことによって,客観的になることそのものが否定されていた。
しかし真理に近づくためには,客観的になるというプロセスを経なければならない。そうでなければ哲学は,思い込みだけでつくられた「常識」と何ら変わらなくなってしまう。常識を乗り越えるためには,一旦は客観的に考えることが必要なのである。
科学であれば,客観的に考えることによって何か得られたならば,それでよしとする。哲学が科学と違うのはその先だ。哲学は,「客観」の後にくる「主観」がメインなのである。つまり,客観的に考えた結果が自分自身にとってどのような意味であるのかを,主観的に考えるのが哲学なのだ。
客観と主観の,どちらに比重を置くかというのが,学問・科学と哲学の違いである。哲学に客観性が不要だ,とはならないわけである。そう考えると,著者は哲学を持ち上げたいあまり,哲学そのものの性質すらゆがめてしまうという失態を犯している。
さいごに
とまぁ,私と著者の考えは対立する部分はあったものの,それ以外は勉強になる部分がたくさんあった。読む価値は十分にあると思う。そんなわけで星3つとさせていただいた。



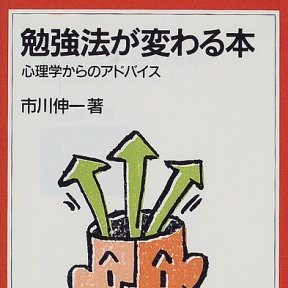
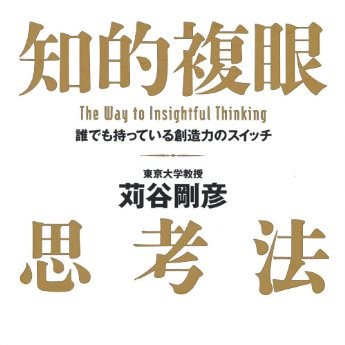
コメント