アズ直子『アスペルガーの子の「本当の気持ち」』要約
アスペルガー症候群の子どもは,その個性のために生きづらさを抱えており,本人もそれをうまく言葉にできない。周囲の大人の知恵や工夫によって,アスペルガー症候群の子どもはスムーズに生活できるようになる。
アスペルガー症候群の本人が直伝する「こうすればうまくいく」ヒント集
本書は,自身がアスペルガー症候群である著者が,自分の人生の中で編み出した「アスペルガーと向き合う工夫・ノウハウ」を書いたものである。
この本は,アスペルガー症候群と関わるすべての人のために書かれている。つまり,著者のように自分自身がアスペルガーである人,アスペルガーの子どもを持つ親,アスペルガーの児童・生徒を受け持つ教師などに役に立ちそうなヒントが,本書では提案されている。
「どうしてちゃんとできないの?」を越える
アスペルガー症候群を含む発達障害の子ども(大人もだが)は,傍からすると「どうしてちゃんとできないの?」と思われてしまうことが多い。
著者によると,「ちゃんとしなさい」と言われても,その「ちゃんと」がよく分からなかったので,何をしてよいのか分からず,動くことができずにいたという。
アスペルガーの子どもの「生きづらさ・不自由」を軽くし,毎日がスムーズに生活できるようにするためには,知恵や工夫が必要になる。では,そのような工夫をどのように考え出すのか。それは,アスペルガーの子どもの気持ちを知ることによって,であるという。
では,「アスペルガーの子どもの気持ち」とはどのようなものだろうか。
アスペルガーの「生きづらい」という気持ちを軽減させる対応策がある
アスペルガー症候群の子どもにとって,毎日は「不安」と「混乱」の連続であるという。ところが,子どもにとって,そのような気持ちうまく表現したり,どうしてほしいかという対策を自分で説明したりするのは容易ではない。
本書では,そのようなアスペルガーの子どもの「生きづらさ」を,著者が代弁している。アスペルガー症候群の子どもにはどのような「個性」があり,それに対してどう対策をすればよいのか。本書のメインはそこである。
ここでは,紹介されていた「対策」の一例をご紹介しよう。なるべく,本書以外ではあまり目にしない対策を選んだつもりだ。
- 「最低限セット」と「大丈夫セット」
- 毎日必ず学校で使うものを「最低限セット」,必要なお助けグッズをコンパクトにまとめた「大丈夫セット」を用意しておけば外出時の緊張感を和らげることができる
- 「妊婦さん作戦」
- 食べ物やにおい,普段の生活での配慮は妊婦さんを気遣うのと同じようにすれば,自然とするべき配慮が見えてくる
- 「儀式」と思っておつきあいする
- 同じ探し物や忘れ物などをしてしまうのを直そうとするのではなく,このままでよい,「想定内のこと」と思う
この他にも,さまざまな対応策が提案されており,その数は32にものぼる。それぞれは,「外出時の工夫」「学校で」などとカテゴライズされており,実践しやすくなっている。
上記に挙げた以外にも「アスペルガーと関わるヒント」が知りたいと思った方は,ぜひ本書を読んでみてほしい。
「気持ちを知る」というのはゴールではない
本書にはアスペルガー症候群に限らず,どのような子どもや,どのような教育場面にも共通して言えることもあった。例えば,以下の引用文にはとても共感できた。
ハンディの有無にかかわらず,他人のことを「わかる」というのは至難の業ではないだろうか。そして,そこを目指すと苦しくなってしまうのでは?(p.28)
アスペルガーの子どもとうまく関わるために,アスペルガーの気持ちを知ろう,というのが本書の基本的な考え方だ。だが同時に,気持ちを理解するというのはゴールではない,とも述べられている。「理解」はあくまで,接し方を知り,うまくサポートするためのものである。
感想:アスペルガー症候群である本人が書いた,という説得力
★★★☆☆
アスペルガー症候群を生きている本人が,「こうしてほしかった」というのには説得力を感じた。まぁ普通にオススメできる本だ。
特に文句があるわけではないのだが,「おおおっ!!」と思わせる要素(←私が読書に求めるもの)がなかったということで星3つ。
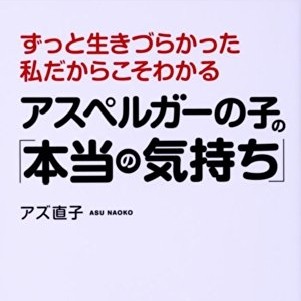


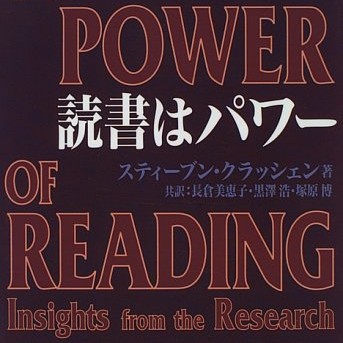
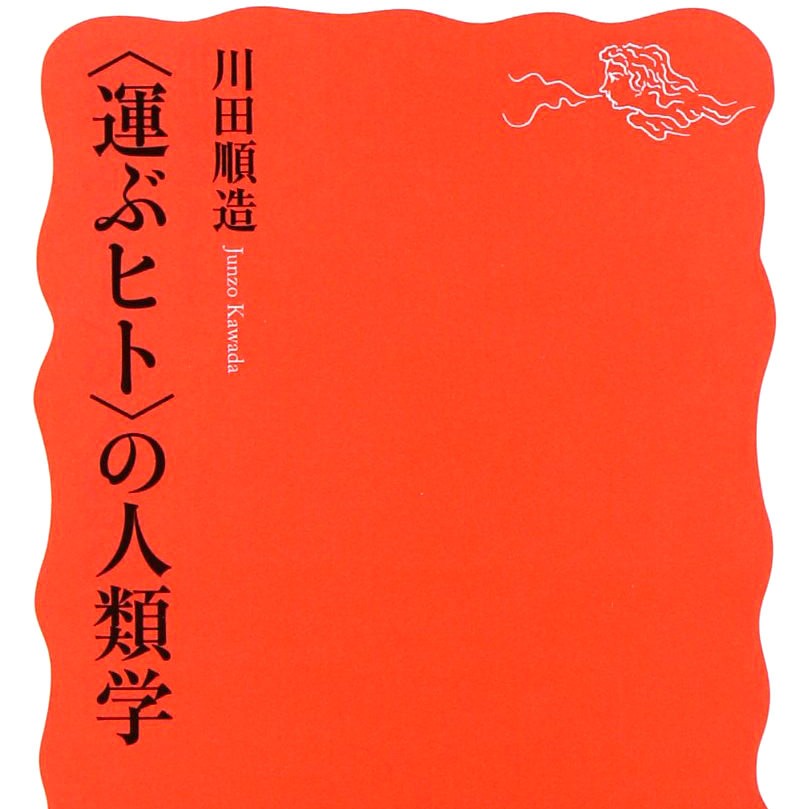
コメント