文献レビュー・論評(literature review)の2つの役割
文献レビューは2つの役割を持つ。
- 特定の研究テーマについての膨大な先行研究を読者が短時間で把握できるようにする。
- 個々の実証研究には扱えない,理論レベルでの結論を示す。
文献レビューと実証研究論文は書き方が違うが,ほとんどの研究者は前者の書き方については学んでいない。本記事が文献レビューを執筆する上でお役に立てればと思う。
文献レビューを書く5種類の目的
文献レビューは,その目的によって5つに分類することができる。
- 新たな理論の構築。
- 既存理論の妥当性の評価。
- 研究状況の概説:特定の現象についてどこまで明らかになっているか。
- 問題点の指摘:仮説上の解決策や,その分野における難しさ。
- 研究の歴史的意義:影響や欠点。
文献レビューの5つの特徴 ―実証研究論文との比較から
文献レビューと実証研究論文は,以下の5つの点において異なる。
- 問いの射程と抽象のレベル:文献レビューはより広範な問いを立てることができる。複数の実証研究の結果を組み合わせることで,より一般的な法則を見つけられる。
- ポストホックな理論構築(post hoc theorizing):文献レビューでは,証拠を集めた後に理論構築することが許されるし,そうすべきである。個々の研究結果を一般化することで,新たな知見が得られるかもしれない。
- ゼロの価値:文献レビューでは好ましい結果を出さねばというプレッシャーが弱いため,既存の研究がいくつかの問いへの答えとしては不十分だと結論づけることもできる。
- 導き出しうる結論の種類:(1)仮説は真である,(2)仮説は今のところ最も有力である,(3)仮説の真偽は知ることができない,(4)仮説は誤りである。
- 方法の一致:複数の異なる研究方法で同一の結果が得られれば,その仮説は信頼できる。
文献レビューによくある9つの間違い
文献レビュー論文においてよく見られる間違いは9つある。
- 序論が不十分:その研究テーマの重要性が書かれていない。論文の早い段階で,理論的枠組みを提示するべき。
- 根拠の範囲が不十分:引用した研究の方法や結果を説明していない。「XはYの原因である」というのは不十分,「Aというサンプルにおいて,Bという方法からCという結果が得られた。したがって,XはYの原因であるということができる」なら十分。
- まとめ方が不十分:個々の研究が理論レベルでどのように一致しているかを書くべき。
- 批判的評価ができていない:研究の誤り・欠点を指摘し,根拠としての有力性を評価するべき。
- 結論を一貫させていない:研究への批判点を踏まえていない結論になっている。
- 意見と事実の混同:ある主張をした人の引用と,その主張を支える根拠を提示した人の引用の区別ができていない。
- 根拠のえり好み:特定の結論に都合のよい根拠だけ集めている。論文の一部を反例の検討に割くとよい。
- 研究ではなく研究者に焦点化:新たに得られた知見や考えを記述しなければならない。方法の1つとして,著者名をカッコ書きにすることがある。
- 現在に留まっている:今後の研究への示唆をしていない。残された課題や問いを指摘するとよい。
本記事は,
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. Review of general psychology, 1(3), 311.
の日本語要約でした。
文献レビューの書き方は,実証研究論文の「先行研究」を書く方法としても役立つものです。この論文はWeb上で無料で読むことができますので,詳しく知りたい方はぜひどうぞ!!

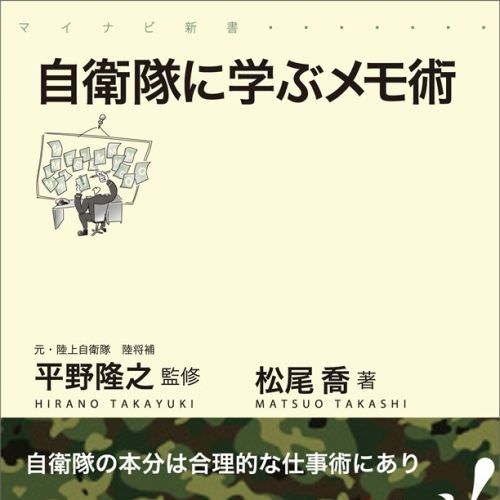
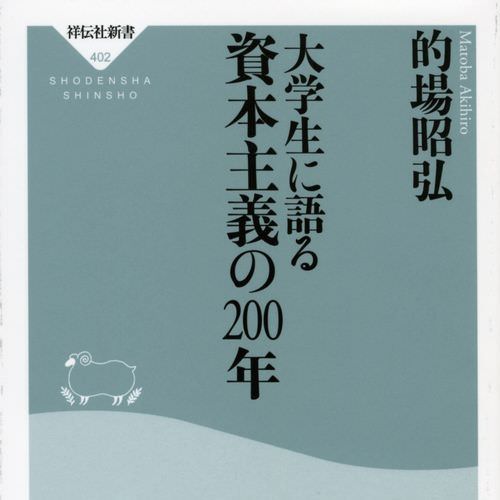
コメント