Sandra Savignon(サンドラ・サヴィニョン)『コミュニケーション能力』要約
[ ][1]
][1]
コミュニケーション能力には,言語的な規則(文法)だけではなく,社会的な規則(社会においてどう振る舞ったらいいか)も含まれる。言語学習は社会化と切り離すことはできず,言語を教えるというのはコミュニケーションを教えるということになるのである。
英語のコミュニケーション能力を育成させる方法
コミュニカティブな授業は「読む・書く・聞く・話す」で考えてはダメ
日本では,授業を構成する要素として「読む・書く・聞く・話す」という4技能の分類法がメジャーだ。だが,著者に言わせればコミュニカティブな授業づくりには,「4技能」とは別のパースペクティブが必要だという。
著者は,オーディオ・リンガル的な「4技能」の代わりに,「5つの要素(components)」を提案している。以下より1つ1つ見ていこう。
言語技術
言語技術は,少しの間,実際のコミュニケーションから一歩下がって,言語の規則・形式を考えることである。具体的には,スペル,語彙,文構造(いわゆる「文法」)などだ。
「言語技術」のゲームの例
- 記憶テスト
- 学習者に10個の品物(ハサミ,フォーク,鉛筆など)を3分間見せ,覚えさせる。3分後,品物を隠し,覚えているものの名前を書き出させる。
- 単語を引く
- 単語が書かれた紙切れを帽子に入れる。その中から学習者に1つ引かせ,その単語を使って完全な文を作らせる。「やさしい単語」と「難しい単語」というように2カテゴリーに分けてもよい。
- ごちゃ混ぜの文章
- 文章の結束性と一貫性に注目させる方法の1つ。1つのテクストの文章をごちゃ混ぜにし,学習者にそれらを正しく並べさせる。
- 私は旅行に出かけます
- 円形連続(round-robin)ゲーム。1人目が “I’m going on a trip and am taking suitcase” などと始め,次の人は前の人の発話を完全に復唱したうえで,2番めのものを付け加える。ゲームが続くにつれてリストはどんどん長くなっていく。バリエーションとして “We went on a picnic and took …” “Happiness is …” “If I had a million dollars I would …” “To succeed in life one must …” などがある。
- 集団記憶喪失
- 文構造や語彙の練習。ナポレオン,エリザベス女王など,有名な人の名前が書かれたカードを学習者の背中に貼り,自分が誰かを当てるゲーム。学習者は歩きまわって “Am I alive?” “Am I an Amercian?” などと質問する。質問の答えは “Yes” か “No” だけにし,同じ人には1回しか質問できない。
- 語彙ビンゴ
- 縦3列,横3列の語彙を並べたボードを用意し,クラスを2つのチームに分ける。それぞれのチームが交互に,ボードにある中の1語を使って正しい文を作っていき,一並びの3つの単語を使って文を作ったチームが勝つ。
- 絞首刑執行人(ハングマン)
- 1つのチームが単語を1つ考え,その単語の字数と同じ数の空欄を先を引いて作る。もう1つのチームは,“Is there an O?” などと質問して,その単語に含まれる文字を推測する。誤った推測をするたびに,ぶら下がった人の形が一筆書きで描かれていく。人の形が完全にできる前に,その単語を推測するのが目標である。
- はみだしものを捜せ
- 語彙のゲーム。一つだけはみだしものの単語を含む語彙リストを用意する。例えば,a) horse, cow, mouse, knife, fish のようなリストを b,c,d,と用意する。学習者は意味の上ではみだしものと思われる単語を書き出す。
- 絵を描く
- 形式より意味を優先する活動。学習者は,与えられた主題を説明するために黒板に絵を描き,他の人が主題を当てる。バリエーションとして,1人が主題を説明し,他の人たちが絵を描くという方法もある。
目的を持った言語
コミュニケーション能力を目標とするプログラムは,すべて意味のある第2言語使用の機会,つまりメッセージに注目しなければならない。
第2言語を自然に使用する機会として,以下のような活動がある。
- イマージョン・プログラム(immersion program)
- 第2言語(L2)を使って,地理・数学・科学・歴史などの科目を教える。
- リンガフランカ(lingua fanca:混成共通語)
- 毎日のクラスの宿題や通知事項などを第2言語(L2)を通じて伝えられ,その場に適したジェスチャーや他の視覚的ヒントとともにコミュニケーションが図られる。
個人的第2言語(L2)使用
最も効果的な言語習得のプログラムは,認知的・知的側面だけではなく,情意的側面に配慮するものである。
情意的側面への配慮として,学習者に選択の余地を与えるというのがある。選択に関わることで学習者は性格や関心が刺激され,自己実現をする機会を得ることになる。
また,活動の種類を増やせば,学習者の参加率は増す。例えばグループ・ディスカッションで静かな人は,ペア・ワークではもっと話すかもしれないし,個人ワークが好きな人がいるかもしれない。
「個人的な言語使用」を取り込む方法
- 互いに知りあう
- 自己紹介(目標,興味など)をする
- 名前と形容詞
- 学習者一人ひとりに自分を説明する形容詞を考えさせる。
- 学生も人間である
- インデックス・カードを配って,名前,住所,感心事,そのコースから学びたいことを書いてもらう。
- 品ぞろえ競争
- 次のような指示が書かれているカードを配る。「次のような人を捜せ。1. 朝食に卵を食べた _____,2. 切手を集めている _____,3. 楽器を弾ける _____ など」これらのリストに当てはまるクラスメートの名前を記入していく。
- 日記
- 1週間の日記をつけさせる。教師は,文法やスタイルについては評価すべきではなく,内容についてのコメントや質問で対処すべきである。
- 個人的語彙
- 学習者が,自分にとって特別な意味がある語彙のリストを作成させる。
- 信じられない!
- 学習者が,個人的な経験をクラスに話す。クラス全体が,その話の信憑性について投票する。目標は,クラスメートをうまく騙すことである。
- 家系図
- 学習者は自分の家族の写真を持参し,クラスに紹介する。これは,「今週の有名人」でもよい。
- グループ分け
- グループ活動の際に,髪の色,名前の最初の文字,背の高さなどの個人の特徴によって学習者をグループ分けする。気まずい気持ちになるような特徴,例えば人種,社会的レベル,国籍などは避ける。
- 物語を話す
- 学習者は円座になり,誰かが物語を話し始める。1人が1文を言い,次の人が1文ずつ付け加えていく。
- ランクづけ
- 歌手,観光地などをランクづけしたリストを作り,グループ内で比較しあう。
- ブレーンストーミング
- グループの1人が,名詞を言い(愛,仕事,母親など),その単語から連想される単語や表現を出す。上級者は,つながれた単語の間の関係を見つけたり,概念的違いについて議論するとよい。
- 調査
- 調査員になった学生のチームが,クラスメートにある主題についての意見を聞く。例えば,理想的な家族の人数,街で一番おいしいピザ屋さん,尊敬する有名人など。調査員は答えを記録し,クラスに報告する。
個人的リーディング活動: 上級レベルの学習者には,自分の楽しみのためのリーディングを促進する。
演劇技術
演劇をカリキュラムに組み込むと,立場や状況に応じた話し方(社会言語的な能力)を身につけることができる。
ロールプレイ活動によって学習者は,(1)普通の授業では経験しえないような状況に対処することができるようになるだけではなく,(2)お互いに気持ちよく協力しあえるような関係(統合的・グループ結束ストラテジー)になる。
演劇・ロールプレイをクラスで行う際には,まず状況を設定する必要がある。学習者に「はい,立って演じなさい!」と言うのではなく,必要な道具を提供しなければならない。
第2言語カリキュラムにおける「演劇技術」の5要素
- パントマイム
- 人の前で演じるという考えにまず慣れる
- アンサンブル活動
- 学習者の動きを伴う言語活動。例えば,グループリーダーの指示に従って,他の人たちは動かなければならない「サイモンが言う」ゲームなど。この活動を大がかりに使ったのが,全身反応教授法(Total Physical Response. TPR)である。
- スクリプトなしのロールプレイ
- 学習者が教師やクラスメートに慣れてくると,スクリプトなしのロールプレイができるようになる。学習者は与えられた状況に応じて,即興の演技をする。
- シミュレーション
- 幅広い状況を学習者に提供する。例えば,砂漠での生存競争,空港建設に反対する市民キャンペーンの組織化,ホテルの手配など。この活動によって,説得したり人に影響を与えたりするなどの社会的スキルを伸ばすだけではなく,創造性にも働きかける。
- スクリプトに基づくロールプレイ
- この活動によって学習者は,対話の意味や趣旨に着目する。例えば,発音,イントネーション,顔の表情,ジェスチャーなどのパラ言語的・非言語的(nonverbal)なコミュニケーションである。
教室を越えて
教室内でのあらゆる活動の目的は,第2言語の世界に参加する準備をすることである。クラスは単なるリハーサルに過ぎない。
第2言語カリキュラムの最終的な効果は,それが周りの世界にどれだけ広がりを見せるか,にかかっている。
教室を越えた第2言語学習のためには,(1)学習者が第2言語コミュニティーに参加すること,あるいは逆に(2)第2言語コミュニティーを教室の中へ招くこと,そして(3)教室の外へ出ていくこと(廊下で教師が第2言語で挨拶する,電話・メール・インターネットの活用など)が必要である。
『コミュニケーション能力』各章の内容
前半は理論や先行研究について,後半はその理論に基づく具体的な授業の作り方について,書かれている。本書の各章の構成を簡単にご紹介しよう。
第1章: コミュニケーション能力」という概念の歴史,理論的背景,定義
第2章: 言語習得研究の発展,「コミュニケーション能力」の理論を支える先行研究
第3章: 学習者の態度・関心が言語習得に与える影響
第4章: 教材の選択,アプローチの例
第5章: CLTに基づくカリキュラムの作成とその具体例
第6章 : テスト・評価方法
感想: 外国語コミュニケーション能力について知りたいならこの本
★★★★★
本書は「コミュニケーション能力」の育成(コミュニカティブ・ランゲージ・ティーチング,CLT)の古典的名著だ。
「コミュニケーション能力」を伸ばす授業づくりをしたい教師だけではなく,教育界で声高に言われている「コミュニケーション能力」とはなんぞや,ということを考えたい人にオススメしたい。
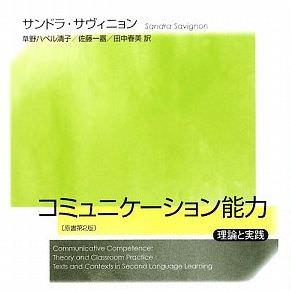
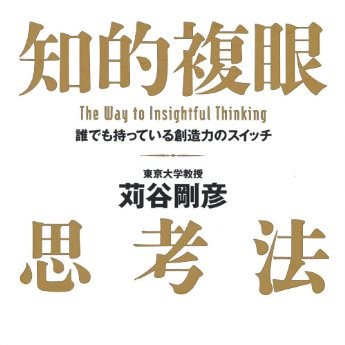
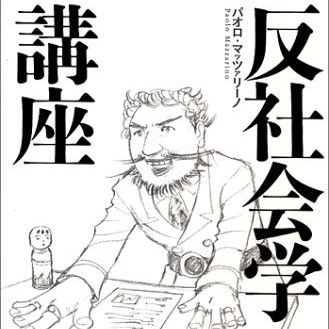
コメント