齋藤孝『読書力』要約
精神の緊張を伴う読書は,自分の中に複雑さを共存させることになり,自己形成を助けてくれる。本を読むことはまた,思考活動の素地をつくり,コミュニケーション力を養うことにもなる。読書力は社会でも求められる能力であり,教育の中でその力を身につけるべきだ。
この本で言う「読書力」とは
齋藤孝の言う「読書力」の定義,そしてこの本のテーマは以下のとおりだ。
多少とも精神の伴う読書(p.ⅱ)
この中には,歴史小説や推理小説など「完全な娯楽」(p.9)としての読書は入らない。
では,「読書力がある」とはどういうことだろうか。それは,
文庫百冊・新書五十冊を読んだ(p.8)
ということになる。文庫本は持ち歩きやすく,読書習慣をつけるのに役に立つ。一方,新書は文庫本と違い,知識情報を獲得する読書力を要求する。上記の量を4年以内で読めるのを「読書力がある」という。
量を読めば何でもいいのか。そうではない。「読んだ」というのには基準がある。
本を読んだというのは,まず「要約が言える」ということだ。(p.18)
逆に言えば,要約が言えれば全体を読んでいなくてもよい,ということになる。半分くらいしか読んでいなくてもいいのだ。
まとめると,以下のようになる。
- 読書力があるとは
- 文庫百冊・新書五十冊を4年以内で読むことができ,読んだ本の要約を言える。
読書力をつけるための4ステップ
読書はスポーツのような「身体的行為」(p.111)であるため,トレーニングを積むことによって上達させることができる。そのステップは以下の4つになる。
1.読み聞かせ 2.自分で声に出して読む 3.線を引きながら読む 4.ギアチェンジしながら読む
「1.読み聞かせ」は幼児~小学生向けのトレーニングだが,それ以降の3つは大人にも応用できる。
「自分で声に出して読む」,つまり音読(素読)することによって言葉が体に馴染み,脳の広い範囲が活発に動き出す。音読の最大の効果は,アイ・スパンを広げることだ。すらすら読むためには読んでいるところの先にまで目を届かせなければならない。音読によってアイ・スパンが広がると,速読ができるようにもなる。
「線を引きながら読む」ことによって読みが積極的になり,後で読み返した時に記憶を呼び起こしやすくなる。以下のようにして三色ボールペンで線を引くと,思考の習慣が身につく。
- 赤=本の主旨からして「すごく大事」だと考えるところ
- 青=「まあ大事」というところ
- 緑=主観的に「おもしろい」と思ったところ
このような色分けをすることによって,主観(=緑)と客観(=赤・青)をスイッチさせる能力が身につき,読解の基本である要約力も鍛えることができる。
「ギアチェンジしながら読む」というのは,「緩急をつけて読む」(p.145)ことである。本の中で大切なところを判断し,そこをじっくりと読み,そうでないところは飛ばし読みをしても構わない。世の中に読まなければいけない本はたくさんある。自分にとって関係のある部分にだけエネルギーを費やすのが合理的な読書の仕方だ。
感想:「読書」と「精神」を結びつけた1冊
★☆☆☆☆
読むことによって人格を形成するという,いかにも日本人らしい考え方。最初から最後まで「主張」で埋め尽くされていて,読んでいて正直うんざりしてきた。
読書は「手段」ではなく「目的」になっている
この本での「読書」と「情報」の関係は次の一文からうかがうことができる。
読書は,〔中略〕複数の優れた他者を自分の中にすまわせることでもある。情報を手に入れることだけが,読書の主目的ではない。(p.69)
知識や情報を得ることは,読書にとってさほど重要とは考えられていないようだ。では何が大事なのかというと,「自分をつくる」とか「自分を広げる」とか,そういうもの。著者はとにかく「本を読むということそのもの」が大事だと考えている。
日本経済の危機が叫ばれているが,読書力の復活こそが,日本経済の地力を上げるための最良の方法だと私は考えている。(p.7)
と言ってしまうほどだ。
「読書で効率よく知識を得たい」という人向けではない
読書そのものを神聖視しているこの本は,次のような方々にはお勧めできない。
- 趣味としてすでに読書経験がある程度ある人
- 役に立ちそうな本を短時間でサッと頭に入れたい人
- 読むということを何らかの形で仕事に生かしたい人
- ガンガン本を読んで研究や学問に生かしたい学生
- 複数の文献を比較して新たな知見を得たい学生
じゃあ誰にお勧めできるか?
- 「読書?ナニソレおいしいの?・∀・」という人
- 本を読まなきゃと思いつつ全然読めていない人
- 自分なりの読書方法を全く持たない人
すぐに実践できる読書テクニックが紹介されている
この本ではいくつかの読書テクニックが紹介されている。これから読書力をつけたいという人には有用と思われる。
- 音読(本記事で紹介)
- 三色ボールペペンで線を引く(本記事で紹介)
- 読書会
- マッピング
- 読書クイズ
特に学生なら,「読書会」がどのようなものかだけでもイメージを持っておくといいと思う。ゼミや自主的な勉強会などにも応用可能なものだからだ。
読書好きが読書好きを育てたくて書いた本。読書好きを目指す方はぜひどうぞ。
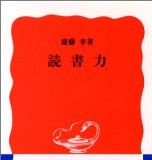



コメント