トラウマ体験を文章に書いて打ち明けることによって身体的・心理的に健康になる,ということは様々な実証研究から明らかになっている。では,なぜ書くことは身体的・心理的健康につながるのだろうか。本論は,250本の実証的論文をメタ分析することによってこの問いに答える。
辛い体験の打ち明け話を書くことによる効果を説明する理論は5つある。メタ分析の結果,そのうち2つは支持されず,2つは部分的に支持され,1つが支持された。

脱抑制理論 (Disinhibition Theory)
脱抑制理論によると,辛い体験についての思いや考えを隠し続けることは危険である。逆に,書くことによってそのような思いを打ち明ければ,ストレスが軽減され身体的・心理的に健康になる。
脱抑制理論が正しければ,書くという体験は次のような被験者により大きな効果をもたらすはずだ。
- 長い間辛い体験について隠し続けていた人
- 辛い体験について隠す傾向にある人(男性,アジア人,抑制的な性格)
メタ分析の結果,脱抑制理論はほとんど支持されないことが分かった。上記のような属性をもつ被験者とそうでない被験者の間では,優位な違いは認められなかった。
認知過程理論 (Cognitive-Processing Theory)
認知過程理論によると,辛い体験を打ち明けることによって身体的・心理的に健康になるのは,その体験について理解を深め頭の中を整理することができるからである。
認知過程理論が正しければ,次のような条件で行った実験が大きな効果をもたらすはずだ。
- 認知過程理論から導き出された指示(トラウマ体験をいくつかの観点から説明するよう求める等)を与える実験
- セッションとセッションの間が長くとられている実験(被験者が処理する時間を十分設けている)
メタ分析の結果,認知過程理論は支持されないことが分かった。認知過程を促す指示のある実験・ない実験や,セッション間の長い実験・短い実験の間には,違いはなかった。
自己制御理論 (Self-Regulation Theory)
自己制御理論によると,辛い体験を打ち明けることで感情を表現・コントロールでき,そのことが自己効力感をもたらす。自己効力感があるので,直面している問題はコントロール可能だと感じることができ,負の感情を軽減させられる。
自己制御理論が正しければ,次のようなことが期待される。
- 書くことによって自己制御を測定する指標値が改善される
- 辛い体験だけではなく成功体験について書くことによっても同等の効果が得られる
メタ分析の結果,自己制御理論は部分的に支持されることがわかった。
打ち明けることによって,自己制御の測定値には優位な成果はみられないが,うつ症状は有意に改善された。また,成功体験について書くことと辛い体験について書くことには優位な違いはなかった(理論どおりの結果)が,このような実験は母数が少ないため現時点で結論を下すことはできない。
社会的統合理論 (Social Integration Theory)
社会的統合理論によると,打ち明けることによって身体的・心理的に健康になるのは,その人と社会との関わり方が変わるからである。
社会的統合理論が正しければ,被験者は実験後に次のような変化を見せるはずである。
- 周りの人に実験のことや打ち明けたトピック,辛い体験のことを頻繁に話す
- 人付き合いが改善される
メタ分析の結果,社会的統合理論は部分的に支持されることがわかった。
1つ目の予測である「周りの人に実験のことなどについて話す頻度」については,優位な違いは見られなかった。一方,何かを根にもつのをやめたり,クラブや集まりに参加したりするなど,人付き合いは改善された。
露出理論 (Exposure Theory)
露出理論によると,辛い体験についての思いや考えについて向き合ったり説明したり追体験したりするのを何度も繰り返すことによって,やがて辛い体験についての思いや考えが消えていく。
露出理論が正しければ,次の3つのことが予測される。
- 打ち明けることによって外傷後のストレス症状が軽減される
- トラウマの病歴を抱えている被験者に特に効果が大きい
- セッションの数や長さが効果の大きさに重要な影響を与える
メタ分析の結果,露出理論は5つの理論の中で最も大きな支持を得た。
外傷後のストレス症状はわずかに軽減され,トラウマの病歴を抱えている被験者を対象とした研究は効果が大きかった。また,3セッション以上の研究と1セッション15分間以上の研究は,3セッション以下の研究と1セッション15分間以下の研究よりも大きな効果を得られた。
おわりに
★★★★☆
以上,Frattaroli, J. (2006). Experimental disclosure and its moderators: a meta-analysis. Psychological bulletin, 132(6), 823-865. の私的和訳・要約である。以下,個人的な感想を書いていきたい。
辛い体験から立ち直るには
辛い体験について書いて打ち明けることが,その経験から立ち直るきっかけの一つになるというのは確かだと言えそうだ。さらに今回は,その理由まで踏み込んだ議論がなされた。まとめると次のようになろう。
辛い体験について書かくことで立ち直るのは,
- 自分の感情をコントロールできるようになり,そのことが自己効力感をもたらすから(自己制御理論)
- 書くことでその人と社会との関わり方が変わるから(社会的統合理論)
- その経験に何度も向き合ったり説明したりすることで,負の感情が消えていくから(露出理論)
である,というのが本論の結論だ。逆に言うと,この3つのいずれかを満たせるのであれば何も「書く」という行為にこだわる必要はないと考えることもできる(実用レベルで考えるならば)。
瞑想や運動,読書などは感情のコントロールや自己効力感に繋がるだろうし,友人と会って相談することも社会との関わり方を変えたり,その経験と向き合うことに繋がる。
なぜ効果的なのか,ということが分かれば様々な解決策に発展していく。本論を読むことで,そのような発見と出会うことができた。
古い理論<新しい理論(?)
今回5つの理論が紹介されたが,歴史的に古い理論が覆され新しい理論がより正しいと証明された,という展開がおもしろい論文だった。
最初の2つの理論「脱抑制理論」「認知過程理論」は古くから提唱されている理論で,この理論をベースとした実験も数多く行われている。それにもかかわらず,それらの実証的研究を総合的に分析すると「脱抑制」の効果も「認知過程」の効果も証明されなかった。
次に出てきた2つの理論「自己制御理論」「社会的統合理論」は,より新しい理論である。自己制御理論は先の2つの理論を補完する形で生まれた。5つの理論の中で最も支持された「露出理論」は最新の理論である。これまで部分的な支持しかされてこなかった理論であるが,本メタ分析によって大きく躍進したといえよう。
ただ,学問の世界においてありがちなことだが,古い理論ほど検証され批判され不備が明らかにされる傾向にあり,新しい理論ほどまだそれがなされず,それゆえに「新しい=より正しい」というように見えてしまいがちだ。
本メタ分析もその例外に漏れず,新しい理論が古い理論を覆す結果となった。辛い体験を書くことがなぜよい効果をもたらすのか,という議論の決着をつけるにはより新しい理論がさらなる検証と批判にさらされる必要があると感じた。

![[図解]書くことによって気分が上向きになる3つの理由 ―250本の実証研究の分析結果](http://issatsu3gyo.wp.xdomain.jp/wp-content/uploads/2019/01/Experimental-Disclosure.png)
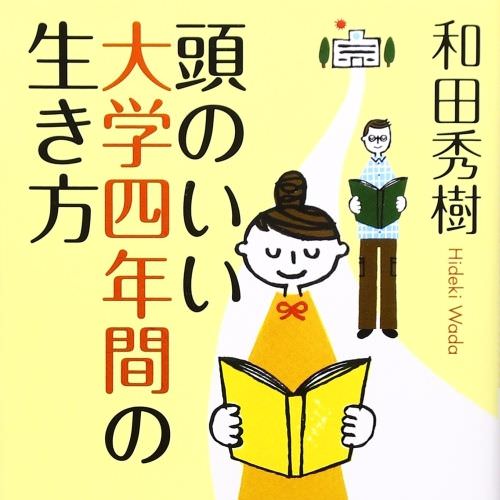
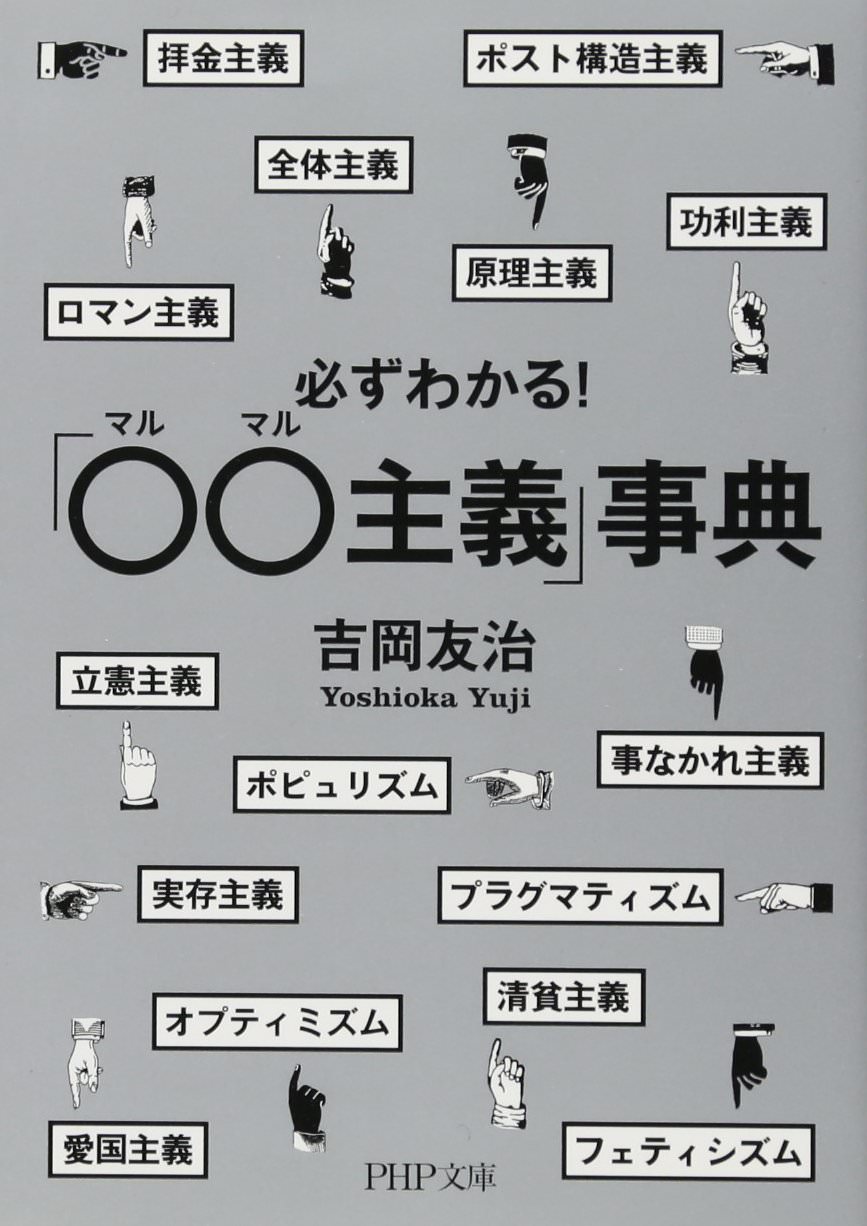
コメント