苅谷剛彦『知的複眼思考法』要約
自分の頭で考えるというのは,ステレオタイプから抜け出して多面的にものごとを捉えることができるということである。知ることと考えることを結びつける「知的複眼思考法」を身につけた人は,「常識」的なものの見方にとらわれず,自分なりの視点から批判的にものを考えることができる。
批判的な考え方を身につける方法
「ガラケーに戻したい」という人は「単眼思考」に陥っているかも
「スマホの時代だからガラケーじゃやばい!」と思いガラケーからスマホに機種変→ラインは便利だがガラケーでも事足りた。むしろ月々の請求が多すぎで,ガラケーに戻したい…。
このような状況の人は少なからずいるのではないだろうか。
周りがみんなスマホだし,便利だと勧められる。時代だからと思ってスマホに乗り換えたはいいが,実際使ってみて自分には必要がないことに気づく。このような,自分の頭で考えずに「常識」に流される考え方を,本書では「単眼思考」とよぶ。
「単眼思考」の人は,身の回りで起きているできごと(先の例でいうと「スマホの普及」)を,自分との関わりで考えられない。「スマホの時代だからスマホをもたなきゃ」というステレオタイプに流され,自分にとって何が重要なのか分からずに,言われるがまま自分には不要なスマホに乗り換えてしまう。
逆に「複眼思考」の人はそのようなステレオタイプに流されず,「スマホの普及」ということを自分との関わりで冷静に捉え直し,スマホに乗り換えるか・乗り換えないか,自分なりの対応を決めることができる。
この本は,そんな「複眼思考」を身につけるにはどうしたらよいか,をかなり具体的に解説してくれる。
「知的複眼思考法」って何?
まずはこの見慣れない言葉,「知的複眼思考法」が何を指しているのかをおさえておこう。
この言葉は,「批判的に考える」「自分なりの視点をもつ」といった知的な行為をちょっとカッコよくネーミングしたものだ。別の言い方をすると,ものごとを鵜呑みにしない態度や「常識」「ステレオタイプ」にとらわれずに考えることをいう。
この言葉の理解を深めるために,この本の中で「知的複眼思考法」とは反対の関係になっているものを列挙してみよう。以下はどれも「知的複眼思考法」とは反対の発想や態度である。
- ものごとには「正解」があると考える(「正解信仰」,p.50)
- 調べれば(知識があれば)問題は解決すると思う(「勉強不足症候群」p.50-52)
- 「どんな問題も個々のケースによってさまざまだよ」と言って思考停止する(p.228)
- 概念(「個性」「創造性」など)を明確な定義づけなしに何となく使う(p.240)
- ものごとを一面的・実態論的に考える(p.271)
逆に,以下のようなことができている人は「知的複眼思考法」が身についているといえる。
- 素朴な「疑問」を明確な「問い」に表現し直すことができる(p.182)
- 個別・具体の事象から細部の事象を切り捨てたり共通点を見つけたりして一般化・抽象化できる(p.232)
- 個別のケースを越えて,概念レベルで問題を考えることができる(p.241)
- ものごとを多面的・関係論的に考える(p.279)
どうすれば「知的複眼思考法」が身につくか
「知的複眼思考法」がいかにクールなものかお分かりいただけただろうか。では,どうすればこんなクールな人間になれるのか。本書は,(1)読む,(2)書く,(3)問いを立てる,(4)ツールを使って考える,という4点を挙げている。
批判的に読むための4つのヒント
「知的複眼思考法」を身につける方法の1つ目は,「批判的に読む」ということである。「批判」は「攻撃」「非難」とは違う。「批判的」に本を読むというのは,
(著者と)対等な立場に立って,本の著者の考える筋道を追体験すること(p.90)
である。そのために,以下の4つのことに気をつけて本を読んでみよう(p.91-97)。
- (1)眉に唾して本を読む
- 読んだことのすべてをそのまま信じたりはしない。おかしいなと思ったら読み返す。
- (2)著者のねらいをつかむ
- 文章の書かれた目的,想定されている読者を見極める。
- (3)論理を追う
- 根拠が薄い主張がないか。データが信じられるものかどうか疑う。
- (4)著者の前提を探る
- 著者が知らず知らずのうちに文章に忍び込ませている前提を探り,疑う。
代案を書いて出すと建設的な批判ができるようになる
「知的複眼思考法」を身につける方法の2つ目は,「批判的に書く」ということである。批判的読書で問題点を探し出すことができたら,次に「代案を出す」ということをしなければならない。非難のような批判ではなく,建設的な批判ができるようにするのだ。
批判的に書くトレーニングとしては「反論を書く」というのがある。では,反論を書くポイントは何だろうか。それは,「違う前提に立って批判する」ということである。「違う前提に立って批判する」ために,以下の点に着目してみよう。
- 著者自身の立場
- 著者の社会観
- 何を論拠に何を問題視しているのか
反論を思いついたら必ず文章にしてみよう。書くことで思考が厳密になり,論理の甘さも見えてくるからだ。また,自分の立場を第三者的に捉えることもできる。
問いを立てるコツは「なぜ」と「どうなっているのか」
「知的複眼思考法」を身につける方法の3つ目は,「問いを立てる」ということである。
「なぜ」と繰り返すことは子どもにもできる。では,大人の「問い」を立てるにはどうすればよいだろうか。それには,問いを「展開」していくことが重要だ。ちょっと問いをずらしてみると,真っ正面からは見えてこなかった側面を捉える視点が見つかる。
問いを「展開」するコツは,因果関係を問う「なぜ」と,実態を問う「どうなっているのか」を組み合わせていくことだ。こう言われてピンとこない人はp.217-227を読んでみてほしい。「最近の大卒就職はなぜ難しいのか」を例に,この2つの問いの組み合わせ方を実演している。
考えることを助ける3つのツール
「知的複眼思考法」を身につける方法の4つ目は,「ツールを使って考える」ということである。本書で紹介されている「ツール」は以下の3つであった。
- (1)関係論的なものの見方
- ものごとの二面性・多面性をとらえ,そこから要因を分解していく
- (2)逆説(パラドックス)の発見
- 「行為の意図せざる結果」「予言の自己成就」があるのではないか見極める
- (3)メタを問うものの見方
- そもそも「なぜそれが問題なのか」に着目する
どれも社会科学では基本となるツールだが,これ以外にも「考える」ことを助けてくれるツールはごまんとある。そんなツールを手に入れたい人は,『フシギなくらい見えてくる! 本当にわかる社会学 』(入門向け)や『命題コレクション 社会学
』(より専門的)などを読むとよいだろう。
複眼的にものごとを捉えるというのは,先に挙げたような思考のためのツールを使って問いの展開のしかたに工夫を凝らすことである。
感想: この1冊は東大レベルの大学のゼミ1年間に値する
★★★★☆
「批判的なものごとの考え方」というのは,大学へ行った人なら身につけている(はずの)スキルだ。ただ,「どのようにしたら」そのスキルを獲得できたのか,を答えられる人はほとんどいないだろう。本の著者の言うとおり,「膨大な本や論文との格闘を通じて」(p.57)自然と身についていくようなものだからだ。
だが,「知らず知らずのうちに身についている」ようなものを,あえて「どのようにして身につけるか」,言葉にした本が本書だ。言葉にするだけではなく,「複眼思考」に関わるスキル一つひとつの実践例を丁寧に示してくれているのが何よりも嬉しい。まさに,大学のゼミや演習の授業でやっているようなことを「本」の上で再現している。
つまり,この1冊を読むことで大学で行われている「ゼミ」を疑似体験できるのだ。私の場合,大学4年間かけてやっと身につけた「考えるスキル」を,この1冊はほぼ網羅してしまっている(ちなみに「考える」支えになる「調べるスキル」は本書の射程にはないが)。
本書の著者が東大の教授をしていたということを踏まえると,本書を読むのは1年間東大レベルのゼミを受けたに値すると言っていいだろう。
あとは,「疑似体験」にすぎないということをお忘れなく。これを演習の授業やゼミなどで実践できるようになって初めて「複眼思考法」が身についたといえる。
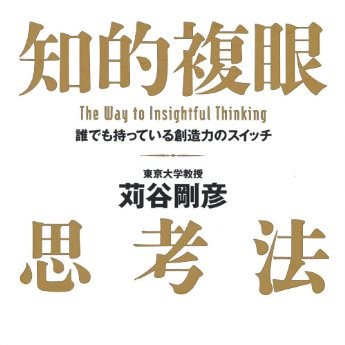


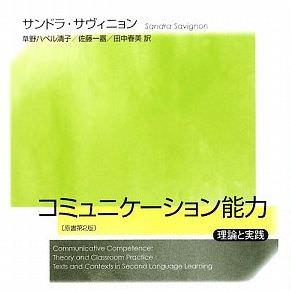
コメント