初めて文学批評理論を学ぶなら『批評理論入門―『フランケンシュタイン』解剖講義』を読んでほしい。批評理論についての解説本はたくさんあるが,それらの理論を「実演」してみせる本はあまりない。そこで本書は,メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』を,様々な批評理論を用いて分析しようというのだ。
理論というものは,定義を聞かされたところでいまいちイメージが沸かない。本書を読んで,文学批評理論というのはどのようなものなのか,どのように使えるかを学ぼう。本記事では,それぞれの批評の「解説」の部分だけをご紹介する。
- 20の文学批評理論まとめ
- 伝統的批評(traditional criticism)
- ジャンル批評(genre criticism)
- 読者反応批評(reader-response criticism)とは
- 脱構築批評(deconstruction)とは
- 精神分析批評(psychoanalytic criticism)
- フェミニズム批評(feminist criticism)とは
- ジェンダー批評(gender criticism)とは
- マルクス主義批評(Marxist criticism)とは
- 文化批評(cultural criticism)とは
- ポストコロニアル批評(postcolonial criticism)とは
- 新歴史主義(new historicism)とは
- 文体論的批評(stylistic criticism)とは
- 透明な批評(transparent criticism)とは
- 廣野由美子『批評理論入門』内容紹介
20の文学批評理論まとめ
伝統的批評(traditional criticism)
道徳的批評(moral criticism)とは
道徳的批評「文学作品は教訓や感動を与えるもの(であるべき)」
道徳的批評は,「この場面は涙なしには読めない」などの印象主義的な論調で分析したり,「ひどい扱いをすると,人は邪悪になる」などの教訓を,作品から得ようとしたりする。また,作品を読むことで,感動や共感を得ようとする。
一方,道徳的・教育的観点からは理解できない作品に対しては,その思想や表現がいかに危険であるかを批判する。学校の先生などがやりそうな批評方法だ,と思っておけばよいだろう。
伝記的批評(biographical criticism)とは
伝記的批評「文学作品は作者の人生の反映である」
登場人物や物語の場面は,作者を反映していると考える。作者に影響を与えたものは何か,登場人物のモデルとなった人物は誰かを,突き止めようとする。
ジャンル批評(genre criticism)
文学作品をいろいろなカテゴリーに分類する考え方を,ジャンル批評という。
本書では,批評例として使われた『フランケンシュタイン』が属する4つのジャンル,すなわち,ロマン主義文学,ゴシック小説,リアリズム小説,サイエンス・フィクションについて紹介されたいた。
ジャンル批評では,対象となる作品において,そのジャンルらしいと思われる点を見つけようとする。
ロマン主義文学とは
ロマン主義文学「自我や個人の経験,無限なるものや超自然的なものこそが大切だ」
- 超自然的なもの例:自然への情愛,亡き友を偲ぶ気持ち,崇高で神秘的な自然描写など
啓蒙主義への反動として現れたロマン主義文学の特徴は,荒涼とした自然の原始的な力や人間と自然の精神的交流に対して鋭い直感を示すことである。
- テーマの例:旅,幼年時代の回想,報われない愛,追放された主人公など
ゴシック小説(Gothic novel)とは
ゴシック小説とは,中世の異国的な城や館を舞台として,超自然的な現象や陰惨なできごとが展開する恐怖小説。ロマン主義文学の中に含まれ,18世紀後半~19世紀初頭を中心に流行した。
ゴシック小説の主要なテーマは,「逃れようのない不安」であり,真実味にかけた内容を仰々しい表現で描くという特徴を持つ。
リアリズム小説とは
リアリズム小説「人生を客観的に描写し,物事をあるがままの真の姿で捉えよう」
リアリズム,ロマン主義の行き過ぎに対する反動として盛んになった。方法としては,非現実的な描写や美化を避け,人生における日常的・即物的側面を写実的に描くという特色がある。
サイエンス・フィクション(science fiction, SF)とは
サイエンス・フィクションとは,空想上の科学技術の発達に基づく物語。科学によって創造されたものが,予期せぬ結果を導くというのが,SFのお決まりの筋書きである。
SFでは,「進歩と破局は不可分である」というテーマが繰り返し出てくる。
読者反応批評(reader-response criticism)とは
読者反応批評「文学作品は,読者に働きかけることによって,意味が与えられる」
文学作品とは,テクストに活発に関わってくる読者の存在を前提したものである,と定義するのが読者反応批評である。
読者によって作品に対する反応の仕方は異なる。そのため,テクストが何を意味しているかではなく,テクストが読者の心にどのように働きかけるのか,という問題に焦点を置く。その意味で,読者は,テクストとの共同作業によって意味を生産する存在である。
脱構築批評(deconstruction)とは
脱構築批評「文学作品には中心的意味なんてない」
脱構築批評とは,テクストが互いに矛盾した読み方を許すものであることを明らかにするための批評。ポスト構造主義(poststructuralism)の1つとして位置づけられることもある。
脱構築批評によれば,テクストとは論理的に統一されたものではなく,不一致や矛盾を含み,「自ら分解している」ものである。1つの正しい解釈があるのではなく,テクストが矛盾した解釈を両立させていることを明らかにするのが,脱構築批評である。
具体的には,原因/結果,明/暗,生/死,意識/無意識などの,二項対立(binary opposition)の解体や,テキストをめぐる異なった解釈のどれが正しいのかというのは決められないとする決定不可能性(undecidability)を示すことを目指す。
精神分析批評(psychoanalytic criticism)
フロイト的解釈
フロイト的精神分析批評「無意識の中にとどめられている抑圧された考えや本能,欲望は,芸術作品などの創造行為などの形をとって現れる」
フロイト的精神分析批評では,作者や登場人物のなかにエディプス・コンプレックスを見出そうとする。エディプス・コンプレックスとは,父に取って代わり母の愛を独占したいという願望のことである。
ユング的解釈
ユング的解釈「文明によって抑圧された人類全体の欲望を明らかにしたものが,優れた文学作品である」
フロイトは人間の無意識と性との関係を強調し,個人の抑圧された欲望の現れに焦点をあてた。しかし,ユングはそれに異を唱え,人間の無意識には,生まれながらにして民族や人類全体の記憶が保有されていると指摘し,それを「集団的意識」と呼んだ。
神話批評(mythic criticism)
神話批評「神話や文学には,個人や歴史を超えた人間経験の「原型」があるはずだ」
- 抽出されるモチーフの例:創造,不滅,英雄,探究,楽園追放,闘争,追跡,復讐など
「原型」とは,集団的意識によって受け継がれてきた原初の心象や状況,テーマなどのことであり,ユングによって名づけられた。
- 「原型」の例:私たちが抑圧したいと思う人格の劣った側面である影,人間が社会に対して演じてみせる仮面であるペルソナ,精神を躍動させるエネルギー源であるアニマ・アニムスなど
ラカン的解釈
ラカンはフロイトの理論を発展させ,「言語」という新たな要素を付け加え,これに焦点を置いた。彼は,無意識を言語として扱い,夢を言説の形として捉えた。
ラカンによると,幼児の発達段階は言語との関係において3つに区分することができる。言語という伝達手段を持たず,母との境界が識別されていない「前エディプス・コンプレックス段階」,母親と自分が別の存在であることを認識するようになる「鏡像段階」,自分(男児)が父と同性であることを知り,父に対してライバル意識を持つようになる「エディプス・コンプレックス段階」である。この時期は,幼児が言語の世界に入っていく時期とほぼ重なりあい,男児は母を失った疎外感を,言語によって埋めるため,女児よりも速やかに言語の世界に入っていく。
ラカン的解釈では,例えば,作品をある登場人物がエディプス・コンプレックスを順調に乗り越えることのできなかった物語として読む。
フェミニズム批評(feminist criticism)とは
フェミニズム批評「文学には,男性による女性の抑圧や,家父長制的なイデオロギーが反映されている」
フェミニズム批評は,性差別を暴く批評として登場した。男性作家が書いた作品を女性の視点から見直し,女性の抑圧を明らかにしたり,家父長制的なイデオロギーが作品をとおしていかに形成されているかを明らかにしたりする。
ジェンダー批評(gender criticism)とは
ジェンダー批評「作品の書き方や読み方は,男女によって本質的に異なるのではなく,文化的規範によって形成される」
男女を本質的に違うものとするフェミニズム批評とは異なり,ジェンダー批評は性別は社会によって形成され押しつけられたものにすぎないと見る。また,もっぱら女の問題に焦点を当てることもしない。
ジェンダー批評は,従来は周縁に追いやられた存在であった同性愛者も対象としている。それがゲイ批評,レズビアン批評であり,それぞれ男性同士,女性同士の関係に着目する。両者を含めて「クイア理論」(queer theory)ともいう。
マルクス主義批評(Marxist criticism)とは
マルクス主義批評「文学作品は,ある歴史時点において政治・社会・歴史などの条件が絡み合って生じた産物である」
マルクス主義批評は,文学作品を「物」として扱い,それがどのような歴史的状況のなかで生まれたのかに着目する。マルクス主義批評家にとって,「歴史」とは対立する社会的な力の闘争である。
文学作品が「物」として歴史的に存在する限り,そのなかには何らかの「闘争」が表現されているはずだ,と考える。たとえ闘争自体をテーマとしていなくても,テクストのなかに,統一を崩す矛盾の要素(例えば,科学技術が進歩しているのに人間の自由は達成されず,人間を新たな隷属状態に至らしめた,など)が含まれているはずであり,そこに「歴史性」を見いだそうとする。
文化批評(cultural criticism)とは
文化批評「文学作品は,ある文化的背景のなかに関係づけられる産物である」
文化研究は,優れた作品をキャノンとして権威づけることを否定し,写真であれ広告であれ同等に扱い,差別しない。文化研究の目的は,価値評価による作品の位置づけではなく,文化的背景における関係づけである。
例えば,ある文学テクストが,時代を経てハイ・カルチャーとロウ・カルチャーとの間をいかに行き来してきたかという過程を検証する。また,原作を,映画やドラマ,漫画などの本案と比較するという研究もある。さらに,時代の文化的背景の中で重要なテーマ(例えば少年非行問題など)を,作品の中から取り出すというアプローチもある。
ポストコロニアル批評(postcolonial criticism)とは
ポストコロニアリズムとは,20世紀後半においてヨーロッパの諸帝国が衰退し,「第三世界」が,西欧の植民地支配から独立したあとの歴史的段階を指す。
ポストコロニアル研究は文化研究の一種で,西洋によって植民地化された第三世界の文化全般の研究を指し,特に文学作品を対象とする場合をポストコロニアル批評という。
ポストコロニアル批評には,2つの方法がある。
第1に,植民地化された国や文化圏から生まれた文学作品を研究するというアプローチ。帝国支配からの脱皮後,第三世界諸国では,植民地主義の文化的影響からの脱皮がいかに図られているか,というような問題に焦点が当てられる。
第2に,帝国主義文化圏出身の作家が書いた作品において,植民地がいかに描かれているかを分析する方法。西洋文化圏のテクストに,植民地主義的言説がいかに刻印され,人種的他者がどのように表象されているかというような問題が,特に注目される。
新歴史主義(new historicism)とは
それまでの歴史主義は,歴史を文学作品の「背景」とみなす。出来事を重視し,歴史を直線的・発展的なものと捉え,特定の時代精神と結びつける。
それに対し,新歴史主義は,歴史をより広範なものとして捉え,社会学や文化人類学などを含む「歴史科学」として位置づける。そのため,他の領域のテクストと文学テクストとの境界を取り払うというやり方をとる。
文体論的批評(stylistic criticism)とは
文体論とは,テクストにおける言語学的要素に着目し,作者が文やテクスト全体の中で,語や語法などをいかに用いているかを科学的に分析する研究方法をいう。
具体的には,一文の長さ,使われている品詞の頻度,文の抽象性,句読点の打ち方などに着目し,そこから人物の特徴や場面の雰囲気を読み取ろうとする。
透明な批評(transparent criticism)とは
「不透明な批評」は,テクストを客体としてみ見て,その形式上の仕組みを,テクストの外側に立って分析する。テクストを言語的な構築物であることを前提とした形式主義的アプローチも,この範疇に属する。
それに対し「透明な批評」とは,作品世界と読者の世界との間に仕切りが存在しないかのように論じる。登場人物が現実の人間であるかのように,テクストから逸脱した憶測に踏み込んでいくようなやり方もある。
文学の世界に入り込んでゆことは,批評において妥当であるかどうかはさておき,読者にその自由が残されていることとは確かだとする。
廣野由美子『批評理論入門』内容紹介
★★★★☆
本書は二部構成となっており,第Ⅰ部「小説技法篇」ではテクストの形式(プロット,語り手,時間,反復,異化など)について,第Ⅱ部「批評理論篇」では作品を解釈するための理論について,解説されている。本記事は第Ⅱ部をまとめたものである。
本書の特徴はなんといっても,文学批評を実演して見せてくれていることだ。実演に使われている作品は『フランケンシュタイン』。この作品を読んだことがなくても,安心してほしい。第Ⅰ部「小説技法篇」のプロットを解説する章であらましが紹介されている。
批評理論は,その定義や手法を紹介されただけでは十分に理解することはできない。実際に使ってみて初めて「ああ,こういうふうにして解釈していくんだ」と腑に落ちるものだ。
もっというと,批評理論というものに初めて触れる人は,そもそもそれが何のために存在しているのかすら分からないだろう。活用されている姿を見て,理論についてもっと知りたいと思うはずだ。
そのような意味で本書は,入門者には絶対おすすめの1冊だ。
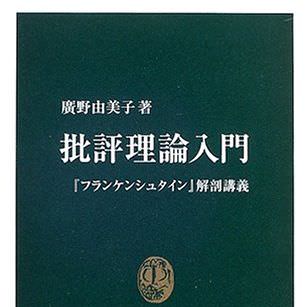

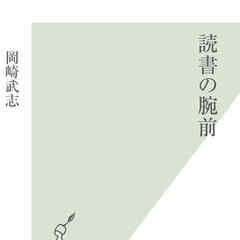
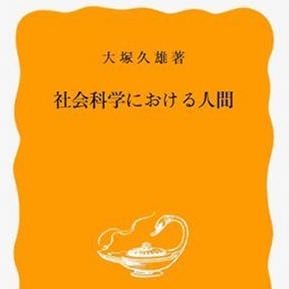
コメント