要約・まとめ『ミステリーの人間学』(廣野由美子)
本書は,イギリス推理小説の系譜に,いかに「人間研究」という特徴が受け継がれているかを紐解き,ミステリーのもたらす作用について探究するものである。
『ミステリーの人間学』の2つの問い
本書には,2つの問いが立てられている。第一の問いは,
文学におけるミステリー性とは何かという根本的な問題…〔後略〕(p.229)
第二の問いは,
ミステリーが人間に及ぼす不思議な作用の「謎」を追求したい…〔後略〕(p.231)
著者はこれらの問いに対し,主に5人の主要なイギリス推理小説家の作品を読み解くことにより,アプローチしていく。
定義: ミステリーとは,謎解きに対する好奇心
「ミステリー」という言葉は,文学や映画のジャンルとして用いられたり,「この作品にはミステリー要素があって最後まで引き込まれる」といったように,狭義のものとして使われたりする。
本書は,「大事なことは最初に」という学術文章のセオリーを守ってくれている。「ミステリー」の定義は序盤で登場する。
さしずめ「ミステリー」とは,謎解きに対する読者の好奇心と理知的欲求を掻き立てる牽引力を秘めた要素とでも言い換えておいたほうがよいだろう。探偵小説は,まさにこの牽引効果を集中的にねらったジャンルである…〔後略〕(p.5-6)
この定義のもと,本書は,イギリスの探偵・推理小説を具体例として,ミステリーの本質を探っていく。
ミステリーは人間研究のツール
本書の第一の問いは,文学におけるミステリー性についてであった。ミステリーや探偵小説は文学の世界に何をもたらしたのだろうか。
文学作品に探偵という存在を導入することによって,人間の悪の秘密を白日のもとに晒し,その罪を完膚無きまで,しかも理路整然と暴くことが可能となる。(p.13)
探偵小説のこのような特徴は,「謹厳で,堅苦しく,上品な」中産階級の規範が支配的であったヴィクトリア朝を生きる作者たちにとって,人間の心を描くうえで重要な「抜け穴」となったのである。
探偵小説の特徴と,その誕生の時代背景を踏まえるならば,第一の問いへの答えは次のようにまとめられよう。文学におけるミステリー性は,人間性の研究をするためのツールとして現れている。
人間の心に触れるというミステリーの作用
第1~5章は5人の作者を取り上げながら,人間性の研究がいかに作品に現れているか,具体的に議論が展開していく。
チャールズ・ディケンズ(第1章)は,人間性の暗黒面の探求をテーマとしていた。ディケンズは犯罪を,人間の心の最も暗い局面に関わる題材として取り上げた。
ウィルキー・コリンズ(第2章)は,人が被害者として陥れられる恐怖感を描き出した。その過程においてコリンズが利用したのが,人間の認識の不確かさである。
アーサー・コナン・ドイル(第3章)のホームズ物語は,語り手ワトソンによるホームズ研究であると同時に,ホームズという鋭い観察者の目を通して見た人間研究として捉えられる。ホームズは,犯罪の解決を人生の「研究(スタディ)」として捉え,推理の際には人間の性情と心理を判断材料としていた。
G.K.チェスタトン(第4章)が作品で用いるトリックはいずれも,人間性に密着した単純な性質のものが多い。したがってチェスタトン作品の推理では,犯罪者の立場に身を置きその精神状態を理解しようとする姿勢がみられる。
アガサ・クリスティー(第5章)のテーマは,罪の問題の追求である。クリスティー作品の推理の根底には,人間性はみな似たり寄ったりだという考え方がある。
さて,第二の問いは,ミステリーによる作用に関わるものだった。第1~5章の内容を踏まえて,第二の問いへの答えを私なりの言葉で表すならば,次のようになる。
推理小説という装置は,人間の心の奥深くにある本性を描き出すことによって,読者に自身を含む人間の精神や心理に触れさせる作用をもたらす。
本書全体を踏まえると,筆者のいう「暴力性やトリックの巧妙さを超えた何かがあとに残るような,上質なミステリー」(p.231)とは,人間研究が推理やトリックと巧く絡み合い,人間の心という真犯人を探り出すものだといえよう。
感想・レビュー『ミステリーの人間学』(廣野由美子)
★★★★★
まず,読みやすい。書き方のセオリーを守っている。各話題を終える前に,一段落をその要約に当ててくれているので,「結局何を言いたかったの?」を見失わない。
また,ちゃんと学問している。引用や参考文献がかっちりしているので,さらに学びたいと思う人にとっても読み応えがある。先述の書き方セオリーという形式面からも,議論や参考文献などの内容面からも,文学研究をしたい学生さんにお勧めしたい一冊だ。
さらに,ミステリーマニアじゃなくても楽しめる!! 私はミステリー好きではあるが,読んだことのある推理小説といえばホームズシリーズくらい。あとはコナンを全巻読んでいるくらい。それでも話題に置いてけぼりにならなかったのは,平坦な書きっぷりと,本書の研究対象となる作者・作品を簡潔にまとめて(ネタバレ含む)くれているからだと思う。
非マニアに優しいからこそ,読んだ後には,本書で扱われた推理小説をいくつか読んでみたい気持ちになることは間違いなしだ。そういう意味において,ミステリー入門書としても大成功の一冊だ。数々の古典推理小説が紹介されているから,次にどんな推理小説を読もうか探している,ミステリー・ファンになりたい人にもお勧め。
本書と出会いは,図書館か本屋をブラついている時にたまたま背表紙が目についたというもの。読んでみて,書きっぷりがやたらと『批評理論入門』の雰囲気と似ているなと感じたら,著者が同じだったのでビックリ。『批評理論入門』は本ブログの「入門・初心者に役立つ!! 20の文学批評理論まとめ」でご紹介済。この方イイ仕事ばかりしますね~。
序章で『名探偵コナン』に出てくる「目暮警部」のルーツも明らかになる本書。少しでもミステリーがお好きなら,楽しく読むことができるだろう。「謎解き」を超えたミステリーの魅力に触れたいあなたに,お勧めの一冊だ。
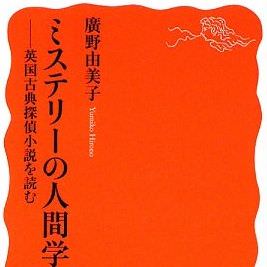

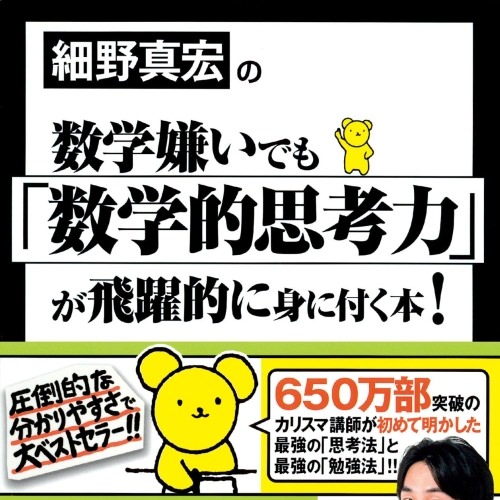
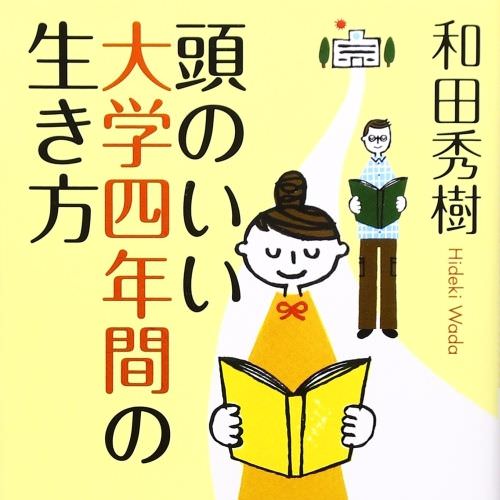
コメント