内田樹『下流志向』要約
子どもたちが学びを放棄するのは,かれらが消費者の目線で学校教育を見ているからである。子どもたちが授業中に不快な態度を示すのは,価値を見いだすことができない学校教育サービスを買わないという意思表示なのである。
子どもたちが学ばない理由は消費社会にある
「新しいタイプの日本人」
子どもたちはなぜ「権利」であるはずの学びを放棄するのだろうか。これが本書の問いである。
「先生,これは何の役に立つんですか?」と訊く子ども,授業のほとんどの時間をおしゃべりや居眠りについやす子ども。それでいながら,「授業を聴く気がないなら学校に来るな」と言われると,激怒する。
著者はこのような子どもたちを,学習についてこれまでとは違う考え方をする「新しいタイプの日本人」だという。
なぜ,このような子どもたちが出現してきたのだろうか。かれらの頭の中で,学びとはどのようなものになっているのだろうか。
人生のスタートは労働ではなく消費になった
今の子どもは,就学以前に消費主体として自己形成を完了している。
昔の子どもであれば,家の手伝いなどの「労働」が社会参加の機会となっていた。しかし家内労働が減るにつれ,今では「消費」が子どもたちの初めて経験する社会的活動になったのである。
昔であれば,労働をすることでまわりから「ありがとう」といわれ,社会的承認と満足感を得ることができていた。
消費者となった子どもが授業を放棄するという当たり前のなりゆき
しかし,今の子どもにはそれをする機会が奪われている。その代わりに,お金さえあれば大人と同じサービスを受けることができるという「法外な全能感」を,消費することから得る。
お金さえあれば一人前のプレイヤーとして扱ってもらえるのだ。知識なんかいらない。
「で,キミは何を売る気なのかね? 気に入ったら買わないでもないよ」
それを教室の用語に言い換えると,「ひらがなを習うことに,どんな意味があるんですか?」という言葉になるわけです。(p.43)
感想:学校教育擁護の立場に偏っていたのが玉にキズ
★★★★☆
学級崩壊や学力低下はなぜ起きるのかということを社会構造的に分析しており,教育問題を「教師や親の怠慢」「本を読まないから」などという理由づけで語ってしまう安易な議論とは一線を画す良書だった。
ただ本書では「学校教育には消費者マインドでは分からない価値がある」ということが前提になっていた。ここに偏りを感じる。
学校教育には意味がないという子どもたちの判断は,もしかすると合っているかも? という立ち止まりがあってもいいんじゃないかと思う。「学校教育には市場原理でははかり切れない価値がある」という主張をするのはよいのだが,それを分析するうえでの前提にもしてしまっていたので,星4つ。
本書のテーマは「学びと労働からの逃走」であったが,本記事では前半の「学びからの逃走」だけをご紹介した。後半の「労働からの逃走」も,圧倒的な説明力で若者の行動を分析している。興味をもった方はぜひ読んでみてほしい。
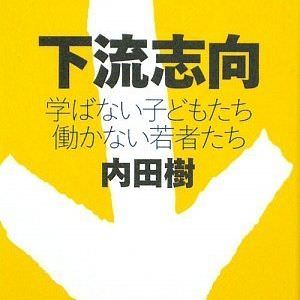


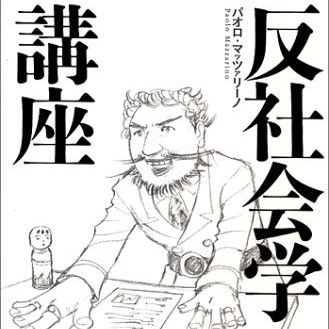
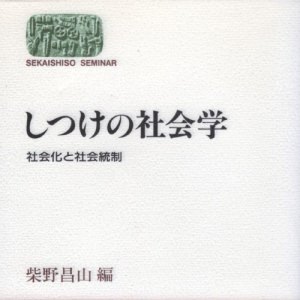
コメント