アラン・ヒョンオク・キム『メタファー体系としての敬語』要約
日本語の敬語の規則・文法は,目上の人を神聖なものとして扱うメタファー体系によってルールづけられている。敬語文法は複雑で例外が多いように見えるが,1つの根源的な原則,つまり〈目上の人=タブー〉によって合理的に説明することができる。
日本人の目上の人に対する意識は明治時代から変わっていない
「お客様は神様」と言っちゃう精神
コマーシャルなどでちょいちょい耳にするフレーズ「お客様は神様です!!!」。私なんかはそれを聞くたびに冷めた気持ちになってしまうのだが,日本語の敬語の規則からすると,こんなフレーズが出てくるのは至極自然なことだという話。
また,「お目にかかる」「足を運ぶ」など字義通りに理解するとおかしな意味になってしまう敬語も,本書の「タブー」という仮説にしたがえば合理的に説明できる。
『メタファー体系としての敬語:日本語におけるその支配原理』は,日本語の敬語の分析から,日本人が「目上の人」をどのようなものとして捉えているのかを明らかにした本である。
敬語は想像上の「目上の人モデル」に対して使われている
本書によると,日本語の敬語表現は本質的にメタファーによって成り立っている。どういうことかというと,敬意を受けるべき「モデル」を作り上げ,その「モデル」に対して敬語の文法規則と適用しているというのである。
「目上の人」といってもいろいろだ。1つ上の先輩から学校の先生,職場の上司などさまざまなレベルがある。だが,それぞれの目上を1つの典型にまとめてしまい,「目上の人モデル」を1つだけ想定するのが日本語の敬語の特徴である。
ではその「目上の人モデル」となっているのはどんなお方か。モデルの特徴は以下の5つだ。
- (1)近づいたり直視したりしてはいけないお方(隔離の原則)
- 直接「会う」ことなどできないので,「お目にかかる」。名指しなどできないので,「お上」「下々の者」。
- (2)むやみやたらと動かず上座にいるお方(労働対極化の原則)
- 「歩きなさる」なんていう動作をイメージさせる生々しい言葉は使わず,「お越しになる」。
- (3)常に上位にいて優越であるお方(位相の原則)
- 差し「上げる」。
- (4)満ち足りており恩恵を与えてくださるお方(恩恵移動の原則)
- 援助など必要ないから「貢がれる」。ありがたいお話を「いただく」。
- (5)使役・許可する権利を持っているお方(使役特権の原則)
- 下位者に決定権などはないので,お手伝い「させて」いただく。命令などできないので,おわかり「いただく」。
日本人の「目上の人」に対する考え方は天皇制だった明治時代のまま
先の5つの特徴を見て,「目上の人モデル」がたいそうやんごとなきお方だと思ったのは私だけではないだろう。日本語の敬語には,「目上の人」をタブー(禁忌・神聖)であるとする前提があるのだ。まさに「神様」なのである。
つまり,日本語の敬語規則は目上の人を「神聖かつ不可侵な存在に擬せ」(p.46 )ているというわけだ。この思考様式,天皇を神としていた明治憲法の時代を彷彿させる。明治時代から日本の「目上の人」に対する考え方は大して変わってはいないのだ。だからこそ「お客様は神様」なーんて言ってしまう人が現れちゃったりするのだろう。
社会階級の平等化に沿って敬語全般が平準化に向かっているのは否みがたいが,その反面,消費大衆向けの巨大型商業主義メディアの波に乗って,敬語がまた幸か不幸か1つの王政復古を経験しているのも面白いパラドックスである(p.248)
敬語の規則はメタファーで説明できる
本書は敬語にまつわるさまざまな疑問や不思議に理論的な説明を与えてくれる。例えば以下のような疑問は,本書の〈敬語=メタファー体系〉仮説でキレイに説明できる。
- 日本人はお礼をするときなぜ「すみません」と言うのか
- なぜ「お食べになる」と言わずに「召し上がる」と言うのか
- 「お宅」「先生方」などでなぜ「お」「方」をつけるのか
それぞれへの「答え」は本書に譲るとして,個人的に面白いと思った「説明」をご紹介しよう。
丁寧・尊敬・謙譲語も実はメタファーだった
「敬語」には丁寧・尊敬・謙譲の3種類があることは,学校でも教えられる。「なぜこんなまどろっこしい言い方をするのか」と思った(ている)人も多いだろう。
本書の〈敬語=メタファー体系〉仮説は,その「なぜ」にも答えてくれる。つまり,メタファーという考え方を使えば,どうしてそのような敬語が使われるのか,という「根本・根源的」な疑問に答えることができるのだ。
簡潔に言うと,丁寧語は言葉という贈り物を包み込む「包装のメタファー」,尊敬語は動作主の労働役割をゼロ化する「自発メタファー」(おエラいさんは動かなくていいですよってヤツ),謙譲語は「奉仕のメタファー」というように位置づけられる。
「敬語の規則」の規則。それがメタファー
敬語の規則・文法として,「お…になる・なさる」「お…申す」などがあることは,日本語の話せる人ならわかるだろう。では,なぜそのような規則・文法があるのかと聞かれて,まともに答えられる人はほとんどいない。せいぜい「目上の人なんだから当たり前でしょ!」くらいの答えしか返ってこなさそうだ。
本書はそれに対し,敬語の規則・文法を生み出すようなメタ規則・文法がある,それがメタファーだ,と答える。そのメタ規則の核となるのは〈目上の人=タブー・神聖なもの〉という,まさに明治時代から変わらぬ日本人的な考え方だ。
感想:新たな視点を与えてくれる一冊
★★★★★
本書は先行研究を丁寧に追いながら論が進めており,参考文献も充実している。また,論の進め方もまるでお手本のようだ。〈先行研究の洗い出し→仮説→仮説の展開→まとめ〉というふうに,丹念に書かれている。
言語学(特に認知言語学)を卒論のテーマにしたいと思っている大学生はもちろん,どうやって論文を書けばよいかよくわからない人にも「学生よ,これが論文だ」とでも言うように作られている,超オススメの本だ。
この分野に興味を持った方は,この本の元ネタとなった『レトリックと人生』も読んでみてほしい。私たちの「理解」という行為がいかに言葉・レトリック・メタファーに依存したものであるのか,ということに気づかされる。
本記事では本の骨格となる第1部を中心に紹介したが,第2・3部を読むと,「敬語」という切り口からここまで掘り下げられるか,と思わされる。個人的には,「敬語」を「メタファー体系」として捉えたというその気づきが秀逸だなと思った。『メタファー体系としての敬語』。タイトルだけで「おっ」と思わせられるでしょ。


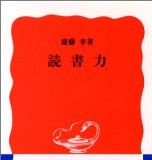
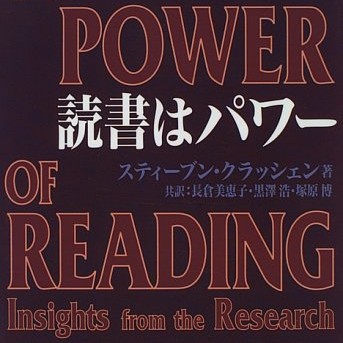
コメント