スティーブン・クラッシェン『読書はパワー』要約
読書は,読み書きや言語の能力を発達させる唯一の方法である。言語教育において最も効果的なのは,子どもが自由に本を選んで読む「自由読書」の環境を整えることである。
100年間の研究をまとめると言語能力は読書だけで身につく
この本の魅力は何と言っても「科学的な」読書論だということだ。同じ読書論でも,日本にありがちな「読書で人間性が豊かになるっっ」というような,精神論的な読書論(例えば[斎藤孝『読書力』][2])とは方向性が全く違う。
以下は,「訳者あとがき」からの引用である。
本書1冊を読めば,これまで約100年間にわたってアメリカ,イギリス,カナダなどで発表された230余の読書についての主要な研究論文,著書,調査結果の内容を知ることができます。いわば現代の「読書論」の集大成といえるでしょう(p.160)
これを読んで分かるように,本書は読書についての研究を総ざらいしたものだが,研究者向けのおカタい感じは全くなく,とても読みやすく書かれている。第二言語習得について勉強したい学生はもちろん,子どもを持つ親,学校の先生(になろうとしている人)にもぜひ読んでもらいたい一冊だ。
子どもを持つ親へ―読書の環境作りをすれば子どもの言語能力は上がる
読み聞かせをしてもらっている子どもは,自分から進んで人一倍読書をする。読み聞かせは,語彙の知識を増やしてくれるだけではなく,読み書き能力の発達においても効果をあげる(p.58-59)。
読書のお手本がいると,子どもたちはますます本を読むようになる。読書を勧めるよりも,親自身が楽しみでの読書を多くする方が,子どもの自発的な読書に効果がある(p.63-64)。
「自由読書」(自由に本を選んで読むこと)は,直接的に文法,語彙,読解指導を受ける(つまり「国語の授業」を受ける)のと同じかそれ以上の効果を持つ。本を読むことで,読解力,文章力,文法力,つづり字力(スペルのこと。本書は英語で書かれた本なので),語彙力を発達させることができる(p.14-29)。
漫画本は学習や言語の発達を妨げるという主張には,科学的根拠はない。むしろ,週に1冊の漫画本を読むと,1年に10万語を読むことになる。ただ,漫画本だけだと言語能力はまずまずのレベルにとどまり,高レベルには達しない。それでも,漫画は漫画以外の読書への橋渡しとなる(p.75-82)。
テレビは,「見すぎる」と読書の妨げになる。しかし,読書量の少ない人と多い人を比べると,テレビを見る時間に違いはない。ただ,まったく読書をしない人はテレビを見る量が多い(p.112-114)。
学校の先生へ―勉強の基礎である読み書き能力は読書で身につく
教室に本を置くことで,子どもたちの読書を促すことができる。図書コーナーの本を近づきやすくすると,本の借り出しが増える。子どもたちにとって利用できる図書の冊数(つまり図書館に置いてある本の冊数など)が多いほど,読書量が多くなる(p.51-52)。
読み書きは指導しなくても伸びる能力である。直接的に教えたり誤りを修正したりしなくても,学校で読書の時間をもうければ,読み書き能力は自然と身につく。意図的に受けた指導の量が多ければ読解力・語彙が進歩する,ということははない(p.32,38)。
語彙や読解のテストは結局「テスト」をするだけに終わる。ドリルや練習問題は読み書き能力を身につけるのには役に立たないだけではなく,読める子と読めない子の差を広げてしまう。そして,読み書き能力の低い生徒から落ちこぼれていってしまう(p.43-46)。
外国語を教える/学ぶ人へ―最も効率的な学習は読書
語彙の習得のためには,読書が効果的である。集中的な語彙指導よりも,読書の方が10倍の速度で語の意味を読み取らせる。言語指導と読書の両方をするより,読書だけに時間を費やした方がよいと示唆されている(p.32)。
テレビよりも読書の方が言語の習得に役に立つ。テレビ番組の語彙数は5,000語以下であるという。小学1年生の語彙数が5,500~32,000語であることを考えると,テレビは言語の入力としては量においても質においても読書に劣る(p.116)。
各章の内容
本書は3章からなっている。それぞれの章の最初には,その章でどのようなことを扱うのかが書かれている。最後に,それを抜粋する。
これらの内容に興味を持った方はぜひ本書を読んでみてほしい。どの章・節もコンパクトにまとめられており,斜め読み・拾い読みもしやすくなっている。
第1章 1. 「自由読書」とは? 2. 「自由読書」が読解力,つづり字力,語彙力,文法力,文章力におよぼす影響 3. 第2言語の習得に「自由読書」が与える効果 4. 「自由読書」と従来の直接的な言語指導の違い
第2章 1. 豊富な図書資料は,「自由読書」にどんな影響を与えるか 2. 公共図書館および学校図書館の役割とは 3. 読み聞かせは,リテラシー(読み書き能力)にどのように影響するか 4. 直接的なはげましやごほうびで,読書はさかんになるのか 5. 漫画本やティーンロマンスの軽読書の効果
第3章 1. 「自由読書」の限界は? 2. 直接的な指導は,いつ行うのがもっとも効果的か 3. 読むことと書くことの関係は? 4. テレビを見ることは,リテラシーにどう影響するのか
感想:内容的には専門書なのに気軽に読めてしまう
★★★★☆
読書が言語能力や読み書き能力(リテラシー)にどれだけ絶大な効果を持つのか,ということを,これでもかというくらい思い知らされた。1つ1つの主張に必ず参考文献を引っ張ってくるという徹底ぶりも好印象。
巻末の参考文献リストを見れば分かるが,この本は完全な専門書なのだ。しかし,構成や文体(翻訳者の努力!!)がとても読みやすく,研究者じゃなくてもスラスラと読めてるようになっている。
内容としては星5つに値する本だが,出版年が1996年とかなり古いということ(その後の研究でこの本の主張のいくつかは覆されているだろう),そして欧米の研究がもとになっているため日本にそのまま応用できない部分があるということを考慮し,星4つとした。
いずれにしても,お子さんをお持ちの方や学校の先生など,教育に関わる人には絶対オススメしたい一冊だ。
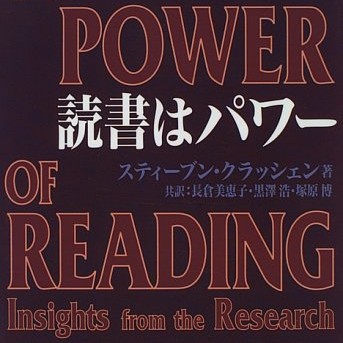



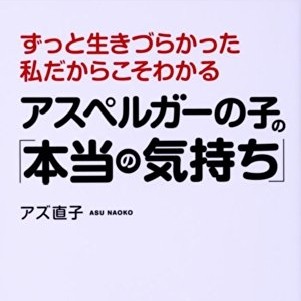
コメント