大塚久雄『社会科学における人間』要約
「社会科学における人間」という問題では,社会科学的な理論的思考の中で,人間がどういうふうに位置づけられるのか,ということを扱う。社会科学において人間は,所属する集団独自の思考様式である人間類型にしたがって行動するものとして捉えられる。
マルクス経済学・ヴェーバーの社会学の優れた入門書!!
本書は,マルクス経済学とヴェーバーの社会学を解説しながら,「社会科学における人間」について論じているものである。
だが本書の話題は,『資本論』でも『プロ倫』でもなく,『ロビンソン・クルーソー漂流記』からスタートする。私は,小学校1年か2年ときに読んだ記憶を掘り起こしながら読み進めていった。
(因みに私は今でも,「一人で無人島に取り残されたら」という話題になると,必ずこの作品のことを思い出してしまう。小さいながらも,それくらい印象深かった作品だ)
そもそもロビンソン物語の著者は,政治経済記者だそうだ。そんな彼がロビンソンのモデルとしたのは,イギリスの中産的生産者層である。彼らの特徴である「現実的で合理的な態度」は,産業革命の原動力ともなったものである。
例えば,それまで商売といえば投機的な要素が強かった。奴隷船貿易で一発儲けてやろう,といういちかばちかの態度だ。それに対し,無人島に漂着した後のロビンソン・クルーソーは,余剰を蓄積・拡大しようとする態度を身につけている。
小麦であれば,食べ尽くしてしまうのではなく一部を畑に撒いて後に収穫しようとするし,野生の山羊であれば,撃ち殺すだけではなく一部は罠にかけて飼い,殖やそうとする。
本書は,このような態度を身につけた人間を「ロビンソン的人間類型」と呼び,この人間類型を軸に,マルクス経済学やヴェーヴァーの社会学について解説していく。
「ロビンソン的人間類型」はマルクス経済学における理論形成の前提
マルクスによると,ロビンソン的人間類型は経済現象を原理的に再現しているそうだ。
マルクスが批判するのは,それまでの経済学が資本主義経済をもとにしていたことだ。資本主義経済では,人間諸個人の活動であるはずの経済活動が,いつのまにかモノ・貨幣の動きであるかのように見えてしまう。
しかし,他の社会形態に目を向けてみると,それは錯覚であることに気がつく。そのことは,ロビンソンの行動からも導き出せる。ロビンソンは無人島漂着後まもなく,簿記をつけ始める。そこには,一定の生産物に費やされる労働時間(人的資源)の表も含まれていた。
マルクスによると,この資源配分こそが経済現象の本質であり,ロビンソン物語はその本質を原理的に再現している。『ロビンソンクルーソー漂流記』とマルクス経済学および『資本論』の関わりに関しては,第Ⅱ部第11章で述べられている。
「資本主義の精神」は「ロビンソン的人間類型」を内から支えるエートス
このタイトルの言い回しは,ヴェーバーのものではなく本書の著者のものなのだけれども。
ヴェーバーは,西ヨーロッパで資本主義経済の発生を担った諸個人を支えたのは,「資本主義の精神」というエートスであると考えた。
(因みにヴェーバーの特徴であるエートス論においては,人間の行動様式を説明するのに,人間の外側(社会)からではなく内側から,本人の自覚なしに押し進める意識形態(=エートス)という概念を用いる)
著者によると,「資本主義の精神」はロビンソンにも現れているという。彼は,優れた経営者であると同時に忠実な労働者だった。彼は将来の必要(需要)に応じて道具や労働力などの資源を合理的に配分し(←経営者),合理的な方法で労働を遂行していた(←労働者)。
もし伝統主義的な労働者であれば,必要以上の賃金はもらおうとしないため,一日働くと次の日は休もうとする。すると,労働力が予測どおりに確保されないため,合理的な経営ができなくなる。
それに対しロビンソン的人間は,賃金が多くもらえることに心理的に誘発されて(ロビンソン的人間の特徴は「合理的な態度」であることは先述のとおり),もっと長い時間労働しようとする。このような「資本主義の精神」に支えられて,資本主義は発生していった。
本書ではヴェーバーの解説は,マルクスの解説の2倍以上の紙面を割いて詳しくなされている。ここでは,『ロビンソンクルーソー漂流記』と関連するところだけご紹介した。
『社会科学における人間』感想
★★★★★
私は基本的に,入門書や解説書には星5つはつけないようにしている。著者のオリジナルアイディアではないので。だが,本書にはつけてしまった。
驚かされたのは,マルクスやヴェーバーを,『ロビンソン・クルーソー漂流記』という切り口から解説しようという発想の独自性だ。それだけではない。解説も分かりやすい。ロビンソンという具体的なイメージ(創作上の人物ではあるが)を思い浮かべながら読むので,難解な理論の説明もスッと頭に入ってくる。
本書は,テレビの大学講座の原稿を加筆して書かれたものということもあり,文体も変に気取ったところがない。かといって,あらぬ方向に脱線することもない。各章の初めと終わりには必ずまとめが挿入されていて,話についていけなくなることもない。
古い本ではあるが,社会科学の基本であるマルクスやヴェーバーを学んでみたい人にはおすすめの一冊だ。
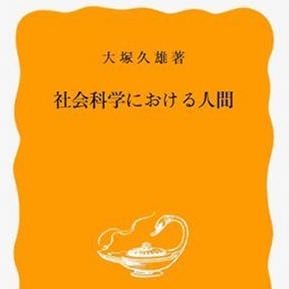

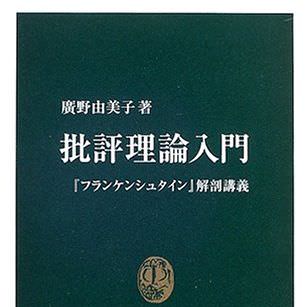
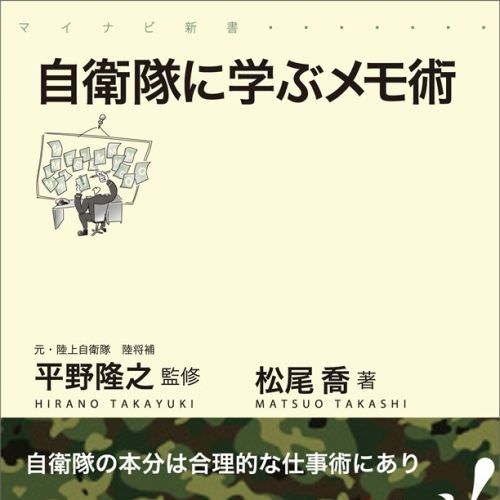
コメント