柴野昌山編『しつけの社会学』要約
現代のしつけは,個性の尊重が強調されている。しかし,実際にとられている方法は子ども本位ではなく命令的なものになっており,明確な達成基準がないために母親は教師の不安や葛藤も招いている。
「強制はダメ,個性を尊重!!」というしつけ・教育がもたらしたジレンマ
本書は,4つの幼稚園への調査をもとに,社会学の理論をふんだんに応用して,しつけを分析した研究書だ。
親や教師が抱える不安や葛藤を中心に記述しており,現代のしつけがどのような構造になっているのかを見事に説明している。7人による編著なので,章ごとにそれぞれの個性が出ていておもしろい。
本記事では,個人的にすごいと思った箇所をいくつかピックアップしてご紹介する。記事の最後に,各章の内容をまとめておいたので,参考にしてほしい。
「子どもは無邪気」という束縛
「子どもというのは無邪気にあそび,よく学ぶものだ」という子ども観が,問題ではないものまでも問題にしてしまっている,と第3章の著者である稲垣は警告する。
子どもを教育の対象としてしか見ず,「大人=社会化,子ども=自然」という対立軸の中に子どもを押し込めることによって,大人は子どもを教育的なまなざしでしか監視できなくなっている。子どもの側も,「あそびのなかで発達する」という大人の期待に応えるように,「子ども」を演じる。
しかし,中には「子ども」定義に合わない子もいる。例えば,「人とあそべない」「カラに閉じこもりがち」というのは単なる性格のはずなのだが,教育的まなざしの中では「子ども」カテゴリーからの逸脱になるため,「問題」となってしまう。
子どもを無邪気な「自然」と見ようとするのは,児童中心主義が背景にあるという。現代においては,子どもに対する強制や教え込みは自律性を妨げるものとして批判され,子どもの発達可能性を信じて子どもの自律を「援助」する児童中心主義的な教育が重視される。
子どもの未来を信じて期待すればするほど,子どもを特定の「自然」に押し込めてしまうというジレンマに陥ってしまう。そして結果的に,「子ども」に当てはまらない子どもを,「教育的配慮」により「子ども」定義に当てはまるよう統制を強めるという,児童中心主義の理念とは逆の帰結をもたらしてしまっている。
子ども自身から引きだしたはずの「自然」な枠組みが子どもを束縛する
大人からの強制や教え込みを排除して子どもの成長を信じようというのが,児童中心主義の理念だ。つまり,「こうすれば大丈夫」という明確な基準がない。その結果起きるのが,しつけ不安だ。
個性の尊重という達成基準の曖昧な目標のために,親・教師は「これでよいのだろうか」という不安に陥る。かといって,教え込みの教育に立ち戻るわけにもいかない。そこで導入されるのが「自然な」枠組みだ。
「自然な」枠組みとして採用されているのは,子どもを成長過程にある存在としてみる発達可能性や性役割がある。どちらも,「子ども自身」の中にその正当性の根拠を求めるという意味で,「自然」なものと思われている。
性役割が社会的に肯定されていた一昔前は,性役割を目標とする「かくれたカリキュラム」があったが,現代の特徴は「結果」的に性役割の社会化をもたらそうとすることだ。しかしここでもまた,「自然な」枠組みを求める結果,特定の「性役割」を子どもたちに強制するというジレンマが生じてしまっている。
「性役割」と「社会構造」とのズレが生じつつある現代にあってなお消滅することのない「性役割のしつけ」は,社会学的に見た場合,たんなる「教育遅滞」とするだけで片づくものではなく,このように教育関係上の相互作用に不可避の「統制」問題からも分析される必要があると思われる。(p.169)
現代のしつけは,目標のない方法論に陥っている
特定の型を教え込むことが否定されることによって,しつけの目的が失われ,しつけ方法に固執するようになる。いつのまにか,しつけというのは叱り方・ほめ方に関する技術という錯覚がおきている。
その結果しつけ知識の大半は,子どもの身体に関する医学的知識,日常生活における実用的な能力に限定された処理的知識,心構えの理論など情緒的で抽象的な知識となっている。
これに加え,日本では伝統的な育児方やしつけ方の再評価がおきており,これがされに親・教師を混乱させている。
われわれの研究の結論としてまず言えることは,速効的かつあらゆるしつけ場面に適用可能な万能のしつけ方策はない,ということである。だが賢明なしつけを実行する心構えや基本的姿勢をもつことは可能である。つまりその場かぎりの速戦即決的しつけ法を求めるのではなく,今日のアノミー的しつけ状況をもたらした歴史的,社会的条件についての明確な知識をもち,巨視的な角度からしつけ場面への対応策を選択する余裕ある構えを形成することは可能であり,大切なことである。(p.299)
『しつけの社会学』各章の内容まとめ・要約
- 序章 しつけの構図―理論的枠組
- 社会学におけるしつけの位置づけの変遷。
- 第1章 幼児教育イデオロギーと相互作用
- B.バースティーンを参考にしながらしつけの4つの様式について。しつけは子どもと大人とのリアリティの共有である。
- 第2章 教師の子供観・教育観
- 教室における教師の役割は,(1)達成の確認,(2)子どもの類型化,(3)秩序の形成である。教師は専門家として振る舞うことで,母親とは一線を画そうとする。
- 第3章 子どもらしさの社会的構成
- 現代では,子どもはあそぶものであり,それによって学習し発達するものだとされている。子どもの側も,その意味を読み取り演じようとするが,そうしない子どもは「問題児」として扱われる。
- 第4章 母親のしつけ理念とアイデンティティ
- 母親は子ども中心のしつけを理想としているが,実際のしつけは統制的になってしまい,しつけの場面や方法をめぐる出口のない葛藤に悩まされる。
- 第5章 社会化エージェントの悩み―母親らしさの逡巡
- 子どもの社会化エージェントとしての役割ももつ母親は,子どもを受容する寛容性とともに子どもにモデルを示す自立性も求められ,一貫性をめぐる困惑が生じる。
- 第6章 性役割の学習としつけ行為
- 明確な基準を失った現代のしつけは,「自然」な枠組として「性役割」を不可視化させた。
- 第7章 学校と規律―現代の異人問題
- 共同体は,秩序が失われそうになると規律を強化する。学校もその例外ではないが,学校は違反者を排除するような「反教育的」なことはできない。そのため,秩序の回復は不十分に終わる。非行をG.ジンメルの異人という観点から分析。
- 第8章 規律・訓練と子どもの自殺―小さなものへの変身
- 逆説的命令と教師・親の権力という二重拘束状況に置かれた子どもは,全体が分解し部分のみに反応するようになり,生命感が剥奪される。G.ベイトソンのダブルバインド(二重拘束状況)の応用。
- 第9章 しつけ思想の変遷(一)―伝統的しつけ思想とその変容,第10章 しつけ思想の変遷(二)―近代化と思想の変化
- 武家社会の江戸時代から大正期までのしつけ思想まとめ。
- 第11章 現代のしつけ状況
- 現代,しつけはしかり方や褒め方に関する技術という錯覚がもたれており,育児というのは医学的,処理的,方法的,抽象的(心構えなど)なものになっている。
感想: 良書は時代を超える!!「今」を見抜く’80年代物
★★★★★
本書は20年以上も前に書かれたものだ。研究書で20年も経っていたらだいたい使い物にならないというのが当たり前だが,本書は現代に通ずる普遍性をもっていた。
扱っているテーマも,声かけ方法や母親の葛藤,学校と規律など,身近なものばかりで「あぁこういう状況あるな」と思える。序章がいきなりの理論ゴリゴリな学問色が出ていて一瞬身じろいでしまうが。
唯一「時代」を感じたのは,受験戦争を扱った第8章だけでだったが,これでさえも,二重拘束状況におかれた子どもの人格形成については,時代を超えた普遍性があった。
最近,「社会学」を名乗りながら,あまり社会学していない本を読んでしまったばかりなだけに,ちゃんと「社会学」になっている本を読めて満足だ。いや,そんな前提などなくてもこの本は十分読みごたえのあるものだった。文句なしの星5つ。
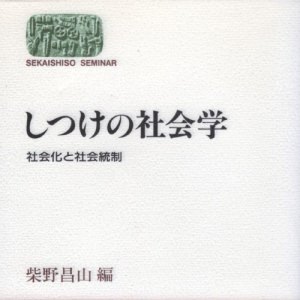

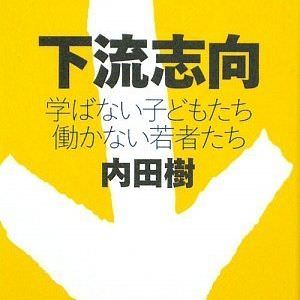
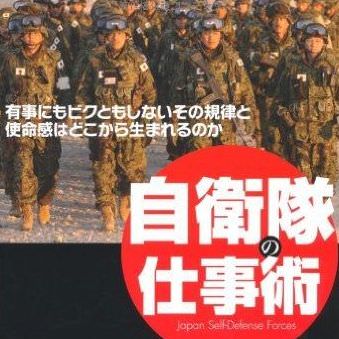
コメント