『道具としての社会学理論』要約・まとめ
本書は,現実の社会を解釈し,自らの行動を決め,社会の改革に進むための「道具」として社会学理論を捉えたいという読者のために書かれている。社会学を社会の解読のための道具として利用しようとすると,理論の蓄積性の欠如とイデオロギー性が障壁となる。本書のねらいは,社会学理論を命題化することで,理論につきまといがちなイデオロギー性を払拭し,理論的蓄積を可能にすることである。
『道具としての社会学理論』目次&各章の要約・まとめ
第1章 社会学の志向
1節 社会学的説明
社会学の論文には以下の7類型があり,中でも説明が社会学の中心をなす。
- 説明:「なぜ」
- 記述:「なにが」「どんな」
- 変化過程の記述:「どのように変化を辿るか」
- 分類
- 評価:「よいかわるいか」
- 予測,応用(政策)
- 検証:説明に対する検証,記述の真偽を確かめる検証
説明には,因果的説明,機能的説明,発生的説明の3分類がある。
- 因果的説明:時間的に先行する事実と後行する事実の間の必然性によって社会的事象を説明すること。
- 機能的説明(目的論的説明):社会事象の結果を原因として説明すること(時間的には因果的説明の逆)。例:猛勉強する(行動)のは優秀な成績で卒業したい(欲求,目標)から。
- 発生的説明:原因が結果を生み,さらにその結果が原因となってまた別の結果を生み出すというように,原因と結果を連鎖として捉えること。
社会学の中心は説明であるが,説明を行うためには記述と分類が正確でなければならない。
社会学が説明しようとしているのは,計画や政策ではない。人間の計画や政策を越えた法則性,あるいは人間の行為の意図されない結果が研究の焦点となってきた。(p.16)
2節 社会学の説明変数
社会学の最終的な目的は,よりよい人間社会をもたらそうとするものである。そのためにはさまざまな社会現象の原因が分からなくてはならない。(p.25)
社会現象を説明する変数(原因)は10に分類することができる。
本書では一つひとつの変数について説明例とともに解説されているので,詳しく知りたい方はぜひ読んでみてほしい。ここでは本書を読んで,それぞれの変数に対して抱いたイメージを書いていきたい(あくまで個人的イメージなので正確性についてはあしからず)。
- 生物的変数:「蛙の子は蛙」「女はおしゃべりだ」「年をとると新しいことを学ぶのは難しい」
- 変性変数:「ツーブロにすると不良になる」
- 本能的変数:「それをやったのは本能からだ」「人間は誰からも承認されなくなると死んだも同然だ」
- 心理的変数:「自慢話が多い人はナルシスト」「日本人は礼儀正しい」
- 人口学的変数:「都会は人が冷たい」「失業率が上がると犯罪が増える」
- 社会構造的変数:「金持ちは貧乏人から搾取する」「女性は細やかな気遣いができる」
- 心理伝染的変数:ヘドバン,満員電車
- 文化的変数:「何でもスマホで済ませようとする若者」
- 生態的変数:「今日は暑かったからみんなダレてた」「北欧の厳しい気候がおしゃれな家具を生んだ」
- 技術的変数:「革命とは未来の“普通”をつくること」
第2章 社会学の変数
先述した社会学の変数の中でも特に必要なものは,(1)社会構造的変数,(2)文化的変数,(3)心理学的変数の3つである。
(1)社会構造的変数は,家族や都市,農村,地域社会などの社会構造に焦点をあてる。個人と社会構造は役割によって結びつけられており,人は役割によって行動する(例:学生,音楽部員,アルバイト先の従業員など)。役割概念を研究することによって,社会構造や個人の理解を深められる。
(2)文化的変数では,文化とは知識,信仰,芸術,道徳,法律,慣習,習慣のようなものを含む複合体とされる。文化は人間のあらゆる面を拘束する(例:狼に育てられた子は人間であっても生肉を食べる)。
文化は個人的機能と社会的機能の2つの側面を持っている。結婚は,他の異性の競争を排除して安心感をもたらす(個人的機能)だけではなく,無秩序な競争を排除して社会の安定をもたらす(社会的機能)。
(3)心理学的変数には以下のようなものが含まれる。
- 動機:救命ボートに乗れば全体が重さ沈んでしまうときに,生きたい思い(欲求)を犠牲にしてボートから手を離す(価値(当為意識))。
- パーソナリティ:「あの人ならやりかねない」などのように,人のパーソナリティを知ればその人の行動が解釈できる。
- 社会化:人に内面化された社会の文化。例:女性は選挙で物価や平和問題に関心を抱く。
- 集団圧力:人はなぜ集団の意見に反対しにくいのか,なぜ世間体を重んじたり,なぜ流行を追うのかという問題を説明する。
- 準拠集団:個人が何かを判断する際の基準となったり,個人の態度や価値観を確立・強化したりする。
第3章 社会学の理論・第4章 社会学の理論Ⅱ
第3章では社会学者ごとに,第4章では理論や分野ごとに,社会学の命題が紹介されている。ここでは紹介しきれないので,各章の内容をリストとして載せておく。
- 第3章の内容
- M・ウェーバーの理論
- K・マルクスの理論
- E・デュルケムの理論
- G・ジンメルの理論
- P・L・パーカーの理論
- 第4章の内容
- 機能主義
- 機能主義的闘争理論
- 交換理論
- 象徴的相互作用主義
- エスノメソドロジー
第5章 理論的課題
1節 マクロ分析とミクロ分析の和解
マクロとは構造(恒常的現象)であり,集団やより大きな社会単位を対象とする。ミクロとは社会過程であり,個人や小さな社会単位を対象とする。
具体的な変数の例をあげれば,次のようになる。
- マクロ変数:人口学的変数,収入分布,文化,政治制度などのあらゆる制度など
- ミクロ変数:交換,状況,自我,印象操作,エスノメソドロジーの再帰性,動機など
マクロ理論とミクロ理論を比べたときに,どちらが社会学理論として正しいのか,という議論が存在してきた。本書はこの対立を「不毛」とし,以下のように述べている。
マクロ分析も,ミクロ分析もそれぞれ認め,さらにそれぞれの分析が持つ多様な視点を認めることにより,社会学理論の深まりが得られるであろう。(p.219)
ちなみにこの至極無難な結論を導き出すのに,約20ページが費やされている。上記の結論は,姿勢や心構えとしてではなく,学問・科学として述べられているといえよう。
2節 社会学理論の蓄積性をめざして
問題を解決するために発展したという意味で,社会学は医学と似ている。しかし,医学と違って社会学は理論の蓄積が乏しい。その原因は,理論間の相互の批判がイデオロギー的側面に集中しているからだ(例:「機能主義は変動を説明できない」「マルクス闘争理論のいう「階級のない社会」はユートピアにすぎない」「交換理論は搾取を正当化している」)。
イデオロギー的対立に巻き込まれないためには,各理論が持っているイデオロギー性の薄い命題・概念・分類・方法論の整理を行ない,有効なものを共有財産として蓄積することが必要である。
感想:入門書であり,事典であり,命題集
★★★★★
本書は少々お堅めとなっており,難しい言い回しや用語があったりする。だが,必ずと言っていいほどそれぞれの項目が具体例で説明されており,分かりやすい。入門者でも理解できる一冊になっている。
各章・節だけでなく,文章の構造がすっきり整理されていて部分読みにも耐えうる。気になったところだけ事典のように引くこともできる。
第3・4章は命題の宝庫だ。要約のしようがないのでここではご紹介できなかったが,後から読み返すことになるのはこの2つの章だろう。
学術書ということで,参考文献も注の形で丁寧に作られている。大満足の一冊だ。
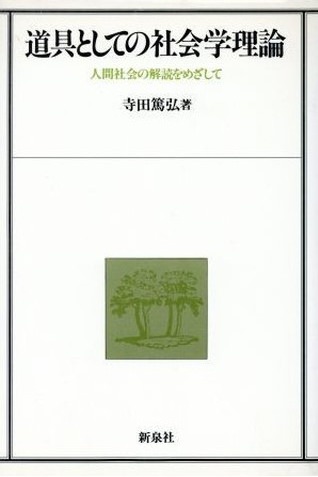



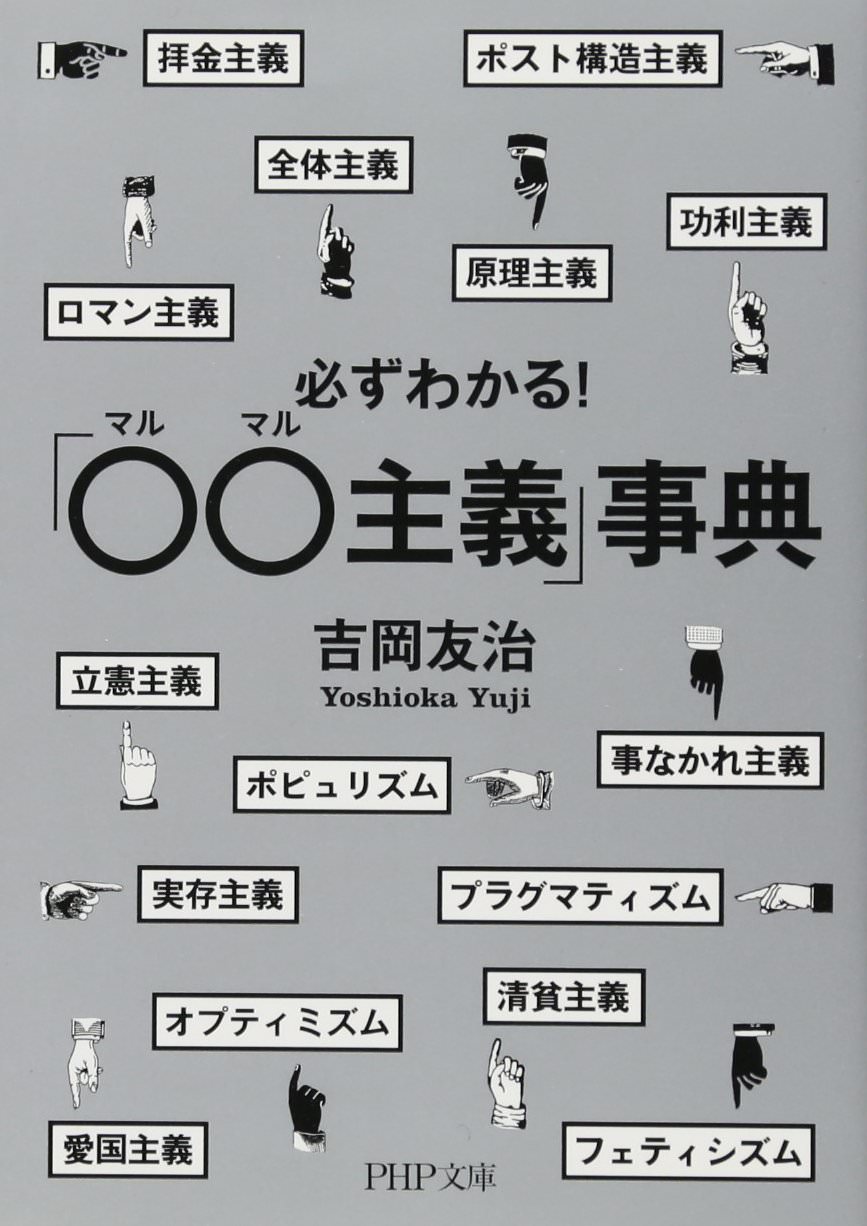
コメント